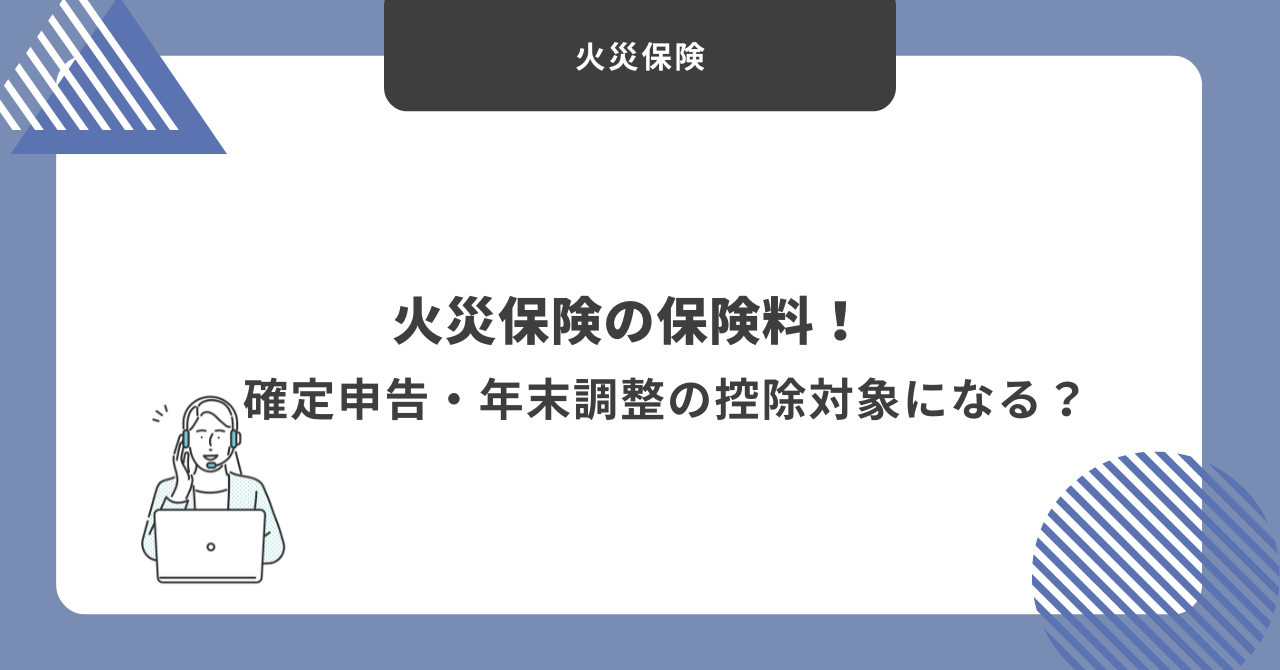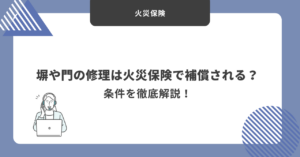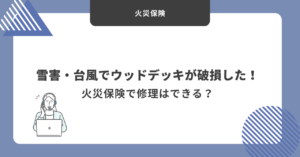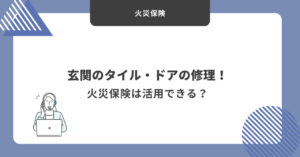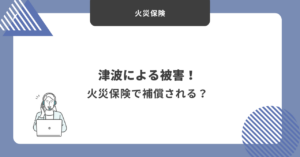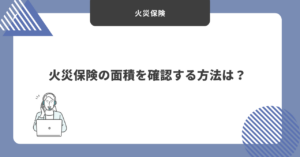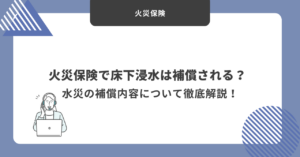火災保険の保険料は、保険料控除を受けられるのかな?
火災保険に加入しているが、年末調整・確定申告でやらないといけない手続きを知りたい。
保険の中には、年末調整や確定申告で申請すれば、保険料の控除を受けられる場合があります。
しかし、火災保険料は保険料控除の対象にはなりません。
今回は、火災保険や地震保険の保険料控除に関して解説します。
この記事を読んだあなたは、火災保険や地震保険の保険料を年末調整や確定申告でどのように申請したら良いか理解できるでしょう。
火災保険は保険料控除の対象?
火災保険は保険料控除の対象外
「火災保険」の保険料は、保険料控除の対象にはなりません。
「生命保険」や「地震保険」は、保険料控除の対象になるため、火災保険も控除対象だと勘違いされる方も少なくないでしょう。
しかし、火災保険は保険料の控除は受けられないため、注意が必要です。
税制改正前は火災保険も保険料控除の対象だった
現在、火災保険は保険料控除の対象ではありません。
しかし、以前は「損害保険料控除」という制度があったため、火災保険も年末調整や確定申告で手続きをすれば控除を受けられました。
2006年の税制改正によって、「損害保険料控除」の廃止1が決まりました。
火災保険料は保険料控除の対象から外れましたが、火災保険とセットで契約することが多い地震保険は控除の対象となります。
セットで契約している場合は、地震保険部分のみの保険料が控除の対象となるため、覚えておきましょう。
地震保険は保険料控除の対象?
地震保険は、保険料控除の対象です。
自然災害による損害を補償するため、税制上の優遇措置が設けられています。
このため、地震保険料は年末調整や確定申告で申請すると、支払った保険料に応じて一定の金額が控除されます。
地震保険料の控除額は?
地震保険の保険料の控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて変わります。
| 1年間の支払い保険料 | 年間控除限度額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 50,000円以下 | 保険料全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 | |
| 住民税 | 50,000円以下 | 保険料の1/2 |
| 50,000円超 | 一律25,000円 |
年間30,000円を支払った場合
所得税控除の対象:30,000円
住民税控除の対象:25,000円
地震保険料控除の対象は?
地震保険料控除の対象となるのは、控除を受ける本人、または生計を同一にする配偶者その他の親族が所有する居住用家屋や生活用動産です。
住宅が夫婦共有名義の場合でも、控除を受けられるのは保険契約者のみになるため、注意が必要です。
賃貸住宅でも控除の対象?
地震保険の保険料控除は、「持ち家」か「賃貸住宅」かによって違いはありません。
賃貸住宅の場合でも、地震保険に加入していれば、控除を受けることができます。
地震保険料の控除を受けるには?

地震保険料控除を受けるには、年末調整または確定申告のいずれかで手続きを行う必要があります。
それぞれの方法について詳しく解説します。
年末調整
会社員や給与所得者の場合、多くは年末調整で控除を申告します。
会社からの指示にしたがって申告の手続きをしましょう。
手続きの流れは、下記の通りです。
地震保険に加入している場合、毎年秋頃に保険会社から「地震保険料控除証明書」が送付されます。
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、控除証明書を添付します。
記入済みの申告書と控除証明書を年末調整時に会社に提出します。
確定申告
自営業者や、年末調整を行わなかった場合は、確定申告で地震保険料控除を申告します。
手続きの流れは、下記の通りです。
保険会社から送付された「地震保険料控除証明書」を手元に用意します。
確定申告書に、控除額を記入します。具体的には「所得控除」の欄に地震保険料を記載します。
申告書と一緒に控除証明書を添付し、税務署に提出します。
保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を紛失した場合は、再発行が可能です。
速やかに保険会社に連絡し、再発行依頼をかけましょう。
法人の火災保険料は経費として認められる
火災保険の保険料は、保険料控除の対象外ですが、会社で必要な火災保険料は経費として計上することが認められています。
そのため、法人で火災保険料を支払っている場合は、経費として計上しましょう。
火災保険の勘定科目
火災保険の仕分けに用いる勘定科目は下記の通りです。
| 勘定科目 | |
|---|---|
| 火災保険料 | 保険料 |
| 2年以上の保険期間の保険料を一括で支払った場合 | 前払費用 |
| 保険料に貯蓄性のある積立金部分を含む契約 | 保険積立金 |
| 受け取った保険金 | 雑収入 |
法人の火災保険料の注意点
法人が火災保険に加入する際には、経費処理や契約内容について特に注意が必要です。
適切に処理を行わないと、税務上のトラブルになる可能性があります。
一括支払いの場合
法人が火災保険料を一括で支払った場合、支払時の経費計上に注意が必要です。
保険期間が1年以内の場合であれば、一括で支払った保険料は全額をその年度の経費として計上できます。
しかし、保険期間が1年を超える場合、契約期間にわたって按分して費用計上する必要があります。
例えば5年分の保険料を一括で支払った場合、1年ごとに5分の1ずつ経費計上をしないといけないため、注意が必要です。
プライベートと業務が兼用の場合
火災保険の対象が、法人の業務用施設だけでなく役員や従業員の居住スペースを含む場合、保険料の按分処理が必要です。
火災保険の契約対象が明確に区分されている場合、プライベートと業務部分の保険料を按分して経費計上します。
例えば、建物全体の50%が業務用だとした場合、保険料の50%を経費として計上できます。
契約書や建物の利用割合に基づいて合理的に按分し、税務署に説明できる根拠を残しておくことが重要です。
まとめ
火災保険の保険料は、保険料控除の対象外となるため、控除は受けられません。
しかし、火災保険とセットで加入する方が多い地震保険については、控除対象となるため、年末調整か確定申告で申告が必要になります。
地震保険に加入されている方は、忘れずに手続きをしましょう。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。