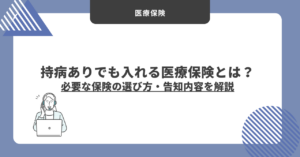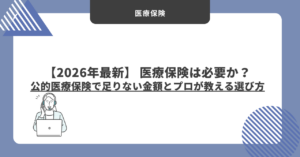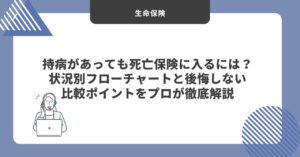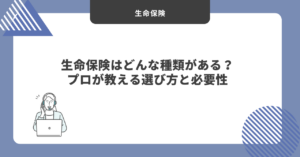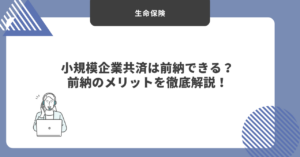小規模企業共済の退職金はいくらぐらいになるのかな?
退職金の計算方法やかかる税金を知りたい。
小規模企業共済の退職金の取り扱いについて知りたい方も少なくないでしょう。
今回は、小規模企業共済の退職金について解説します。
この記事を読んだあなたは、小規模企業共済の退職金制度について理解できるでしょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主向けの退職金制度です。
将来の退職金を積み立てるための仕組みであり、掛金は全額が所得控除の対象となります。
これにより、税金の負担を軽減することが可能です。
共済金(退職金)は、退職や廃業時に受け取ることができ、受取方法も一括や分割から選べます。
共済金(退職金)の受取時には、退職所得控除が適用されるため、税負担が軽減されるメリットもあります。
小規模企業共済の退職金(共済金)の種類
小規模企業共済では、主に下記のような共済金が用意されています。
個人事業主の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 | 備 考 |
|---|---|---|
| 共済金 A | 個人事業を廃業した場合 | 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。 |
| 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したことにより廃業した場合は「準共済金」となります。 | ||
| 共済契約者の方が亡くなられた場合 | ‐ | |
| 共済金 B | 老齢給付 | 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象です。 |
| お仕事を続けたまま、共済金を請求できます。 | ||
| 準共済金 | 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合 | 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。 |
| 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡した場合 | ‐ | |
| 解約手当金 | 任意解約 | 共済契約者による任意の解約です。 |
| 機構解約 | 掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。 | |
| 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合 | 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。 |
会社等役員の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 | 備 考 |
|---|---|---|
| 共済金 A | 会社等が解散した場合 | 会社が破産した場合も該当します。 |
| 共済金 B | 疾病・負傷により役員を退任した場合 | ‐ |
| 65歳以上で役員を退任した場合 | 退任日が平成28年3月以前の場合は、疾病・負傷以外の理由による退任をしたときは、65歳以上であっても「準共済金」となります。 | |
| 共済契約者の方が亡くなられた場合 | ‐ | |
| 老齢給付 | 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象です。 | |
| お仕事を続けたまま、共済金を請求できます。 | ||
| 準共済金 | 法人の解散や疾病・負傷によらず、65歳未満で役員を退任した場合 | ‐ |
| 解約手当金 | 任意解約 | 共済契約者による任意の解約です。 |
| 機構解約 | 掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。 |
共済金の種類が豊富であることが、小規模企業共済の大きな特徴です。
小規模企業共済の退職金はいつもらえる
小規模企業共済の退職金は、主に下記の2つのケースで受け取ることができます。
・廃業した場合
・65歳以上、15年以上掛金を支払った場合
廃業した場合
廃業した場合、小規模企業共済の退職金を受け取ることができます。
廃業手続きが完了した後、共済金の請求を行いましょう。
掛金の納付状況や契約内容に応じて、受取額が決まります。
ただし、複数の事業を営んでいる場合には、すべての事業を廃業した場合となります。
1つの事業は廃業したけれど、他の事業はそのまま営んでいる場合は共済金は受け取れないため注意が必要です。
65歳以上、15年以上掛金を支払った場合
65歳以上で、かつ180ヶ月以上掛金を支払った場合に、退職金を受け取ることができます。
この給付金請求を「老齢給付」と言います。
受取方法は一括または分割から選べるため、ライフスタイルに応じた受取方を選択できます。
退職金(共済金)を受け取った場合の税金

一括で受け取った場合
一括で退職金を受け取った場合、「退職所得」として所得税が課税されます。
退職金から退職所得控除額を差し引き、その残額の半分に対して課税されます。
(退職金-退職所得控除額)×50%=退職所得
このため、実質的に税負担が軽減されることになります。
一括受取は、退職後の資金計画を立てやすいためおすすめです。
分割で受け取った場合
分割で退職金を受け取った場合、「雑所得」として所得税が課税されます。
分割受取の場合、毎年の所得として扱われます。
そのため、受取額が多い年には税負担が増える可能性があるでしょう。
分割受取は、長期的な資金計画を立てる場合に便利ですが、税金の影響を考慮する必要があります。
小規模企業共済の退職金をもらう前に死亡した場合は?
小規模企業共済の契約者が退職金を受け取る前に死亡した場合について解説します。
受取方法
契約者が死亡した場合、遺族が共済金を受け取ることが可能です。
受取人の受給権順位1は、下記の表の通りです。
一般的な順位とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。
| 受給権順位 | 続柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位者 | 配偶者 | 内縁関係者(戸籍上の届出はしてないが、共済契約者が亡くなった当時、事実上婚姻と同様の事情にあった方)も含む |
| 第2順位者 | 子 | 共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していた方 |
| 第3順位者 | 父母 | |
| 第4順位者 | 孫 | |
| 第5順位者 | 祖父母 | |
| 第6順位者 | 兄弟姉妹 | |
| 第7順位者 | そのほかの親族 | |
| 第8順位者 | 子 | 共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方 |
| 第9順位者 | 父母 | |
| 第10順位者 | 孫 | |
| 第11順位者 | 祖父母 | |
| 第12順位者 | 兄弟姉妹 | |
| 第13順位者 | ひ孫 | |
| 第14順位者 | 甥・姪 |
受け取った場合の税金
死亡時に共済金を受け取った場合、「みなし相続財産」として相続税の申告が必要です。
相続税は、受取額に応じて課税されるため、遺族の負担が発生します。
ただし、相続税には基礎控除があるため、一定額までは非課税となります。
このため、遺族は受取額や相続税の計算について事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
小規模企業共済の退職金制度は、経営者や個人事業主にとって老後の生活資金を準備するために大切な制度です。
廃業や退職時には、適切な手続きを行い、税金の優遇措置を最大限に活用しましょう。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。