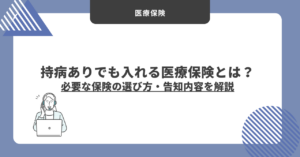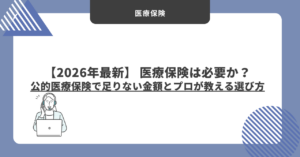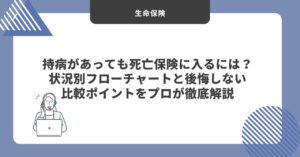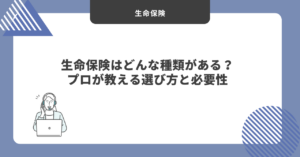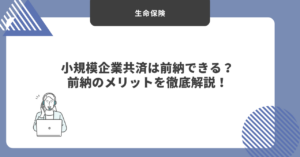小規模企業共済について知りたい。
個人事業主やフリーランスが退職金を準備するのに最適な保険は何?
小規模企業共済に加入しようか悩んでいる個人事業主やフリーランスの方も少なくないでしょう。
今回は、小規模企業の経営者や個人事業主を対象に、小規模企業共済についての基本的な情報を解説します。
この記事を読んだあなたは、小規模企業共済の概要やメリット・デメリットなどについて知識を深められるでしょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が退職後の生活資金を積み立てるための退職金制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、経営者や役員が事業をやめる際に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備することができます。
共済金は、事業の廃業や退職時に受け取ることができ、掛け金は自由に設定できるため、経営者にとって非常にお得な制度です。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済に加入できる1のは、主に下記のような人々です。
・個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方
・理容・美容室などのサービス業を個人経営している方
・個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方
・個人で農業を営んでいる方
・法人化していない個人医院、弁護士・税理士などの士業の方
・株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方。
・合名会社、合資会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)。
・「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員。
・企業組合、協業組合の理事または監事の方。
・農業の経営(営利目的)を主として行う農事組合法人の理事または監事の方(非営利を主とするものを除く)。
・士業法人の業務執行社員の方。
また、従業員数が20人以下の企業が対象であり、法人格を持たない事業者も含まれます。
このように、幅広い層が加入できるため、多くの小規模企業が利用しています。
小規模企業共済の掛け金
小規模企業共済の掛け金は、月額1,000円から70,000円までの範囲で自由に設定できます。
掛け金は500円単位で選択できるため、経営者の経済状況に応じて調整が可能です。
また、掛け金は毎月の支払いが必要ですが、途中で変更することもできるため、柔軟な資金管理が可能です。
納付方法は口座振替となり、支払い方法は下記から選択できます。
・月払い
・年払い
・半年払い
毎月18日に本人名義の預金口座から引き落としがされます。
掛け金の税務上の取り扱い
小規模企業共済の掛け金は、全額が所得控除の対象となるため、課税所得を減少させることができます。
実質的な税負担を軽減することが可能です。
税務上の取り扱い2は、受け取る年齢や受け取り方法などによって異なります。
| 共済金などの受け取り方法 | 税務上の取扱い |
|---|---|
| 共済金(死亡除く)または準共済金を一括で受け取る場合 | 退職所得扱い |
| 共済金を分割で受け取る場合 | 公的年金等の雑所得扱い |
| 共済金を一括・分割併用で受け取る場合 | (一括分)退職所得扱い(分割分)公的年金等の雑所得扱い |
| 遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) | (相続税法上)みなし相続財産 |
| 65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 | 退職所得扱い |
| 65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 | 一時所得扱い |
| 個人事業主が法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合 | 退職所得扱い |
| 12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 | 一時所得扱い |
小規模企業共済の共済金の種類
小規模企業共済では、主に下記のような共済金が用意されています。
個人事業主の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 | 備 考 |
|---|---|---|
| 共済金 A | 個人事業を廃業した場合 | 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。 |
| 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したことにより廃業した場合は「準共済金」となります。 | ||
| 共済契約者の方が亡くなられた場合 | ‐ | |
| 共済金 B | 老齢給付 | 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象です。 |
| お仕事を続けたまま、共済金を請求できます。 | ||
| 準共済金 | 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合 | 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。 |
| 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡した場合 | ‐ | |
| 解約手当金 | 任意解約 | 共済契約者による任意の解約です。 |
| 機構解約 | 掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。 | |
| 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合 | 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。 |
会社等役員の場合
| 共済金等の種類 | 請求事由 | 備 考 |
|---|---|---|
| 共済金 A | 会社等が解散した場合 | 会社が破産した場合も該当します。 |
| 共済金 B | 疾病・負傷により役員を退任した場合 | ‐ |
| 65歳以上で役員を退任した場合 | 退任日が平成28年3月以前の場合は、疾病・負傷以外の理由による退任をしたときは、65歳以上であっても「準共済金」となります。 | |
| 共済契約者の方が亡くなられた場合 | ‐ | |
| 老齢給付 | 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象です。 | |
| お仕事を続けたまま、共済金を請求できます。 | ||
| 準共済金 | 法人の解散や疾病・負傷によらず、65歳未満で役員を退任した場合 | ‐ |
| 解約手当金 | 任意解約 | 共済契約者による任意の解約です。 |
| 機構解約 | 掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。 |
共済金の種類が豊富であることが、小規模企業共済の大きな特徴です。
小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリットを紹介します。
掛け金が自由に設定できる
小規模企業共済のメリットは、掛け金を自由に設定できる点です。
経営者は自身の経済状況に応じて、月額1,000円から70,000円までの範囲で掛け金を選ぶことができます。
資金繰りが厳しい時期でも無理なく続けられるため、多くの経営者に支持されています。
全額が所得控除になる
小規模企業共済の掛け金は全額が所得控除の対象となるため、税務上の大きなメリットがあります。
課税所得を減少させることができ、実質的な税負担を軽減することが可能です。
特に、所得税や住民税の負担を軽減したい経営者にとって、非常に有利な制度です。
退職金の代わりになる
小規模企業共済は、退職金の代わりとして加入する方が多いです。
個人事業主やフリーランスなど、退職金がない方が自分で退職金を準備するために加入します。
事業を廃業したり、退職した際に受け取る退職金(共済金)があることで、安心して老後の生活を送れるでしょう。
貸付制度がある
小規模企業共済には、貸付制度も用意されています。
急な資金需要が発生した際にも、共済金を担保にして融資を受けることが可能です。
経営者にとって非常に心強いサポートと言えるでしょう。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済のデメリットを紹介します。
早期に解約をすると元本割れする場合がある
小規模企業共済は、早期に解約すると積み立てた金額よりも受け取る共済金が少なくなり、元本割れする可能性があります。
そのため、長期的な視点での運用が求められます。
短期間での解約を考えている方は注意が必要です。
掛け捨てのリスクがある
小規模企業共済は、掛け捨てのリスクも伴います。
共済A・Bの場合には、納付月数が6ヶ月未満だと掛け捨てになります。
また、準共済金及び解約手当金の場合は、納付月数が12ヶ月だと掛け捨てになります。
このようなことがあることを考慮して加入を検討しましょう。
共済金を受け取る時に課税される
共済金を受け取る際には、課税されることがあります。
受け取った共済金は所得として扱われ、課税対象となります。
事前に税務上の取り扱いを確認しておくことが重要です。
小規模企業共済へ加入する方法
小規模企業共済への加入方法は、窓口での手続きとオンラインでの手続きの2つあります。
窓口での手続き方法
近くの商工会や金融機関の窓口で申し込みすることが可能です。
申し込みをする場合には、必要書類を持参して加入手続きを行います。
小規模企業共済の取扱いかあるかを事前に確認することをおすすめします。
オンラインでの手続き方法
オンラインで手続きをすることも可能です。
その場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要になります。
手続きの手順は、画面通りに行いましょう。
具体的な手続きについては、公式サイトでの確認をおすすめします。
まとめ
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者にとって、退職後の生活資金を積み立てるための有効な退職金制度です。
加入資格や掛け金の自由度、税務上の処理など多くのメリットがありますが、元本割れや掛け捨てのリスクも存在します。
メリット・デメリットをしっかりと理解し、自身の状況に合った選択をすることが重要です。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。