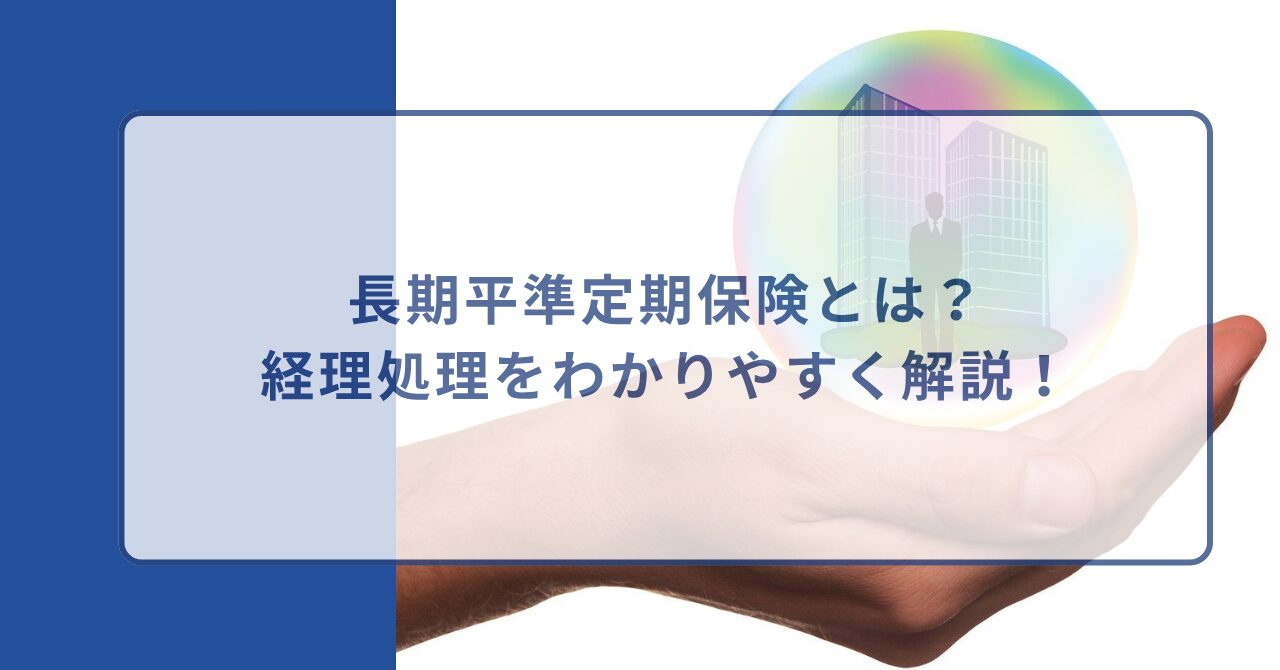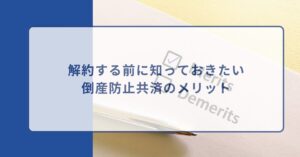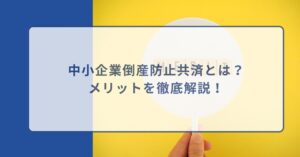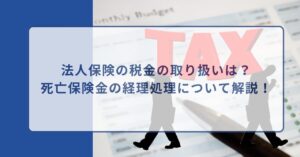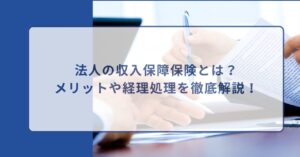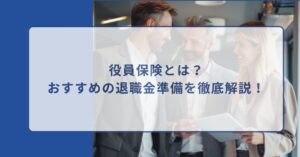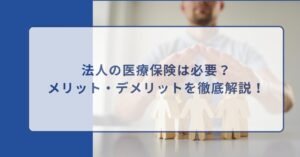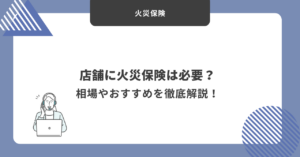長期平準定期保険について知りたい。
長期平準定期保険の経理処理の方法がいまいち分からない……
税制改正により長期平準定期保険のメリットが分からないという方も少なくないでしょう。
今回は、長期平準定期保険について詳しく解説します。
この記事を読んだあなたは、長期平準定期保険のメリット・デメリット、経理処理の方法まで理解できるでしょう。
長期平準定期保険とは?
長期平準定期保険は、主に法人向けに設計された生命保険商品で、保険期間が長いことが特徴です。
通常の定期保険と異なり、保障が100歳まで続くことが多く、経営者や法人が利用します。
一般的な定期保険と比べて、保険期間が長く解約返戻金が一定期間ほぼ一定になるという特徴があります。
そのため、企業のリスク管理や退職金の準備などに役立ちます。
長期平準定期保険と逓増定期保険の違い
長期平準定期保険と逓増定期保険の違いを解説します。
保険金額
長期平準定期保険は、契約時に設定した保険金額が変化せず一定です。
逓増定期保険は、契約期間が進むにつれて保険金額が増加します。
保険料
長期平準定期保険は、保険料が一定です。
逓増定期保険は、保険金の増加に合わせて決まるため、初期は保険料が安く、後半ほど高くなる傾向があります。
解約返戻金
長期平準定期保険は、解約返戻金が契約時に設定された保険金額に基づいて計算されます。
逓増定期保険は、途中で急激に増えて、その後減少していきます。
長期平準定期保険と逓増定期保険の違い【比較表】
| 長期平準定期保険 | 逓増定期保険 | |
|---|---|---|
| 保険金額 | 一定 | 増加 |
| 保険料 | 一定 | 増加 |
| 解約返戻金 | 一定 | 途中で増えて、その後減少 |
長期平準定期保険のメリット
長期平準定期保険のメリットを紹介します。
長期間の安定した保障
長期平準定期保険は、保障が長期間にわたって続くため、被保険者に万が一があった場合も長期間安定した死亡保障を確保できます。
特に、中小企業にとっては経営者や役員の万が一に備えて、リスクマネジメントが可能です。
経営者や役員に万が一のことがあった場合、取引先や銀行から信頼を失うことも考えられます。
しかし、長期平準定期保険に加入し高額な保険金を設定することで、万が一のときに経営を立て直すことが可能です。
保険料が一定
長期平準定期保険は、保険料が一定であるため、予算の計画が立てやすく経営の安定性を保つことが可能です。
そのため、企業の財務管理に適しています。
また、長期平準定期保険は定期保険のため、貯蓄型保険よりも保険料が割安です。
一定の割安の保険料でしっかりと保障を得られるため、おすすめです。
解約返戻金を活用できる
長期平準定期保険は、解約返戻金があるため、必要に応じて資金を活用することが可能です。
そのため、企業の資金繰りを柔軟に行うことができるでしょう。
長期平準定期保険のデメリット

長期平準定期保険のデメリットを紹介します。
短期の解約には向いていない
長期平準定期保険は、短期間での解約には向いていません。
早期に解約すると、解約返戻金が少なく、支払った保険料を下回る可能性が高いです。
そのため、無理をして加入することはおすすめできません。
税務上の扱いが複雑
税務上の扱いが複雑であるため、経理処理において注意が必要です。
税務上のメリットを最大限に活かすためには、専門的な知識が求められます。
税理士や保険会社に相談することをおすすめします。
長期平準定期保険の経理処理(保険料を支払う場合)
長期平準定期保険は、保険料の半分を損金算入できる「節税保険」として活用されていました。
しかし、2019年の税制改正によりルールが変更されて、損金算入できる保険料が少なくなりルールが厳格化されました。
最高解約返戻率が50%以下の場合
最高解約返戻率が50%以下の場合、保険料は全額損金算入が可能です。
経理処理が比較的簡単で、企業の財務に対する影響も少ないでしょう。
最高解約返戻率が50%以上70%以下の場合
最高解約返戻率が50%以上70%以下の場合、保険料は全額損金算入が可能です。
被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば、全額を損金算入できます。
しかし、30万円以上の場合は、期間によって損金算入できる割合が変わるため注意が必要です。
具体的な割合については、保険会社に確認することをおすすめします。
最高解約返戻率が70%以上85%以下の場合
最高解約返戻率が70%以上85%以下の場合、保険開始当初40%までの期間は保険料の40%を損金に計上して、残り60%を資産に計上します。
保険料の一部が損金算入されますが、計算が複雑になるため保険会社に相談することをおすすめします。
最高解約返戻率が85%以上の場合
最高解約返戻率が85%以上の場合、損金算入の計算が難しくなるため、経理処理には特に注意が必要です。
税理士や保険会社などの専門家に確認することをおすすめします。
長期平準定期保険の経理処理(保険料を支払う以外の場合)
保険料を支払う以外のケースにおける経理処理についても、以下に示します。
払済に変更した場合
長期平準定期保険を払済に変更した場合、「払済変更時の解約返戻金相当額」と「それまでに資産計上している保険料」との差額を益金か損金として算入します。
同じタイプの払済定期保険に変更する場合は、前払保険料を契約終了時まで据え置きすることが可能です。
解約した場合
解約した場合、解約返戻金が発生します。
前払保険料と解約返戻金の差額が少ないか多いかによって、下記の通り計上します。
前払保険料よりも解約返戻金が少ない場合:差額を「雑損失」として損金算入
前払保険料よりも解約返戻金が多い場合:差額を「雑収入」として益金算入
死亡した場合
死亡した場合、死亡保険金が支払われます。
今まで資産計上していた前払保険料を取りやめ、死亡保険金との差額を雑収入として益金算入します。
まとめ
長期平準定期保険は、法人向けの生命保険商品として多くのメリットがありますが、デメリットや経理処理の複雑さも伴います。
そのため、適切な知識を持って、保険選びや経理処理を行うことが重要です。
特に、税務上の扱いや解約返戻金の計算については、保険会社や税理士など専門家に確認することをおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。