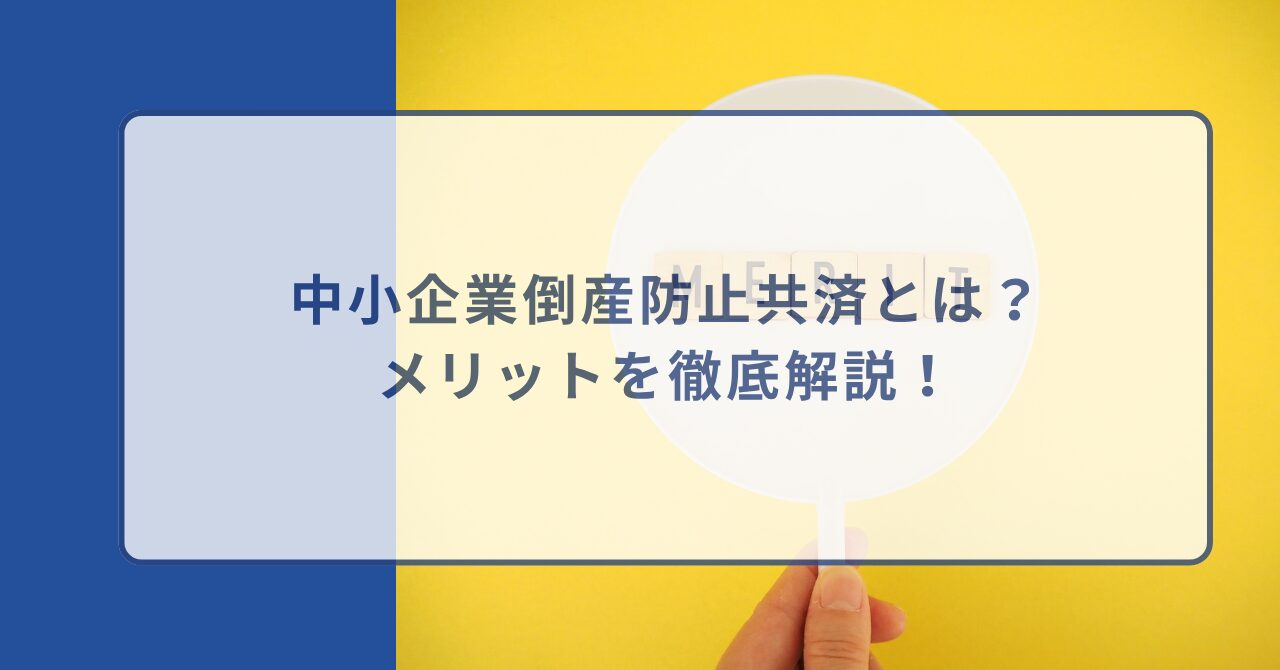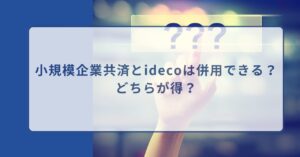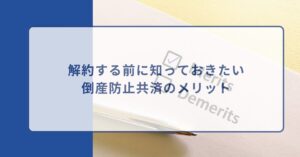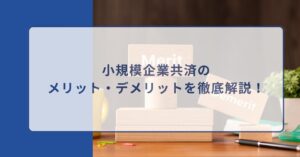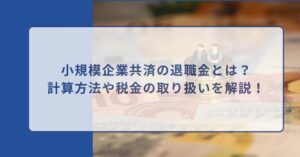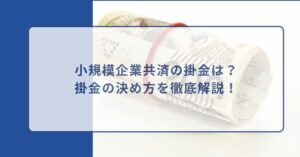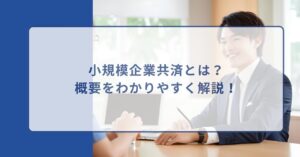中小企業倒産防止共済について知りたい。
中小企業倒産防止共済に加入するメリットは?
中小企業倒産防止共済について知りたい方も少なくないでしょう。
今回は、中小企業倒産防止共済のメリットについて解説します。
この記事を読んだあなたは、中小企業倒産防止共済の具体的な内容や加入条件、メリット・デメリットを理解できるでしょう。
中小企業倒産防止共済とは?
中小企業倒産防止共済は、経営セーフティ共済とも呼ばれ、中小企業が取引先の倒産などによる経営危機に備えるための制度です。
毎月一定の掛金を支払うことで、万が一の際に資金を借り入れることができます。
この制度は、特に中小企業にとって重要なリスクヘッジ手段となるでしょう。
倒産による連鎖的な影響を防ぐために設計されており、経営の安定を図るための強力なサポートが受けられます。
中小企業倒産防止共済の掛金
中小企業倒産防止共済の掛金は、月額5,000円~200,000万円までで5,000円単位で自由に設定できます。
掛金は、事業の利益に応じて調整可能であり、経営者が無理なく支払える金額を選ぶことが可能です。
さらに、掛金は損金計上や経費として扱うことができるため、節税効果も期待できます。
中小企業倒産防止共済の加入条件
業種ごとの要件
中小企業倒産防止共済は、特定の業種に対して加入要件が設けられています。
個人事業主の場合
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 300人以下 |
| 卸売業 | 100人以下 |
| サービス業 | 100人以下 |
| 小売業 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 300人以下 |
| 旅館業 | 200人以下 |
会社の場合
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
具体的な要件は、共済の公式サイトや窓口で確認することができます。
1年以上の事業実績がある
加入条件の一つとして、1年以上の事業実績が求められます。
企業が安定した経営を行っていることを確認するための基準です。
新規開業の企業や、事業を始めたばかりの企業は、残念ながらこの条件を満たさないため、加入が難しいでしょう。
事業実績があることで、共済の信頼性が高まります。
中小企業倒産防止共済に加入できないケース
中小企業倒産防止共済には、加入できないケース1も存在します。
・住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
・事業に係る経理内容が不明の方
・中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
・納付すべき所得税を滞納している方
・掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
・不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
・現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)
これらの条件を事前に確認し、加入の可否を判断することが重要です。
中小企業倒産防止共済に加入するメリット

中小企業倒産防止共済に加入するメリットを紹介します。
節税効果が高い
中小企業倒産防止共済の最大のメリットの一つは、節税効果です。
掛金は損金計上や経費として扱うことができるため、法人税や所得税の負担を軽減することが可能です。
特に、利益が出ている時期に加入することで、税負担を大幅に減少させることができるでしょう。
無担保・無保証で資金を借りられる
中小企業倒産防止共済に加入していると条件はありますが、無担保・無保証で資金を借りることができます。
取引先の倒産時以外でも事業資金を借りることが可能です。
通常、金融機関からの借入には担保や保証人が必要ですが、中小企業倒産防止共済を利用することで、スムーズに資金を調達することができます。
取引先が倒産した場合に借入できる
取引先が倒産した場合、売掛金が回収できなくなるリスクがありますが、中小企業倒産防止共済に加入していると、迅速に借入が可能です。
これにより、資金繰りの悪化を防ぎ、連鎖倒産を回避することができます。
特に中小企業にとって、この制度は非常に重要なリスクヘッジとなります。
中小企業倒産防止共済に加入するデメリット
中小企業倒産防止共済に加入するデメリットを紹介します。
元本割れする可能性がある
中小企業倒産防止共済に加入しても、元本割れのリスクがあります。
原則40ヶ月未満で解約した場合は、解約手当金が元本割れしてしまいます。
早期解約だけではなく、長期間にわたって掛金を支払った場合でも、最終的に受け取る金額が掛金の総額を下回る可能性があるため、注意が必要です。
事業を1年以上継続していないと加入できない
中小企業倒産防止共済は、1年以上の事業実績がないと加入できないため、新規開業の企業や事業を始めたばかりの企業は利用できません。
この条件は、経営の安定性を確保するためのものですが、スタートアップ企業にとっては大きなハードルとなります。
解約手当金が課税対象になる
中小企業倒産防止共済を解約した際に受け取る解約手当金は、課税対象となります。
解約を考える際には税金の影響を考える必要があります。
特に、解約手当金が大きな金額になる場合、税負担が高くなるため注意が必要です。
まとめ
中小企業倒産防止共済は、経営の安定を図るための重要な制度です。
加入することで得られるメリットは多く、特に資金繰りのサポートや節税効果が大きな魅力ですが、デメリットも存在します。
加入を検討する場合は、自社の状況やニーズに応じて、最適な選択を行いましょう。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。