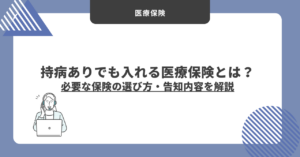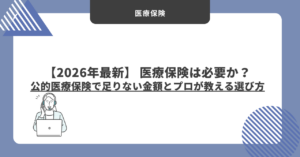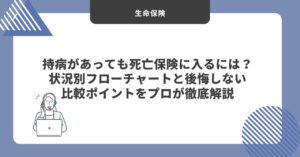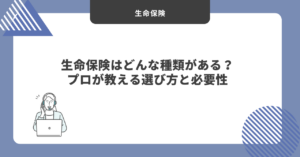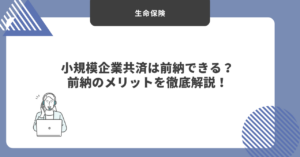小規模企業共済を利用して節税はできる?
小規模企業共済に加入することで節税のメリットがあるのはどんな人?
節税目的で小規模企業共済に加入しようか悩んでいる方も少なくないでしょう。
今回は、小規模企業共済の節税効果について解説します。
この記事を読んだあなたは、節税のためには小規模企業共済をどのように活用すれば良いか理解できるでしょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者を対象とした共済制度です。
主に、将来の退職金を積み立てるための制度であり、掛金は全額が所得控除の対象となります。
これにより、課税所得を減少させることができ、結果的に税金を軽減する効果があります。
加入者は、月々の掛金を1,000円から最大70,000円まで自由に設定でき、必要に応じて増額や減額も可能です。
将来の備えをしながら、税金対策も同時に行える点が大きな特徴です。
小規模企業共済の節税効果をシミュレーション
小規模企業共済の節税効果をシミュレーションで解説します。
節税効果の計算シミュレーション
節税効果のシミュレーション1は、下記の表の通りです。
掛金の全額所得控除による節税額一覧表
| 課税される所得金額 | 加入前の税額 | 加入後の節税額 | ||||
| 所得税 | 住民税 | 掛金月額10,000円 | 掛金月額30,000円 | 掛金月額50,000円 | 掛金月額70,000円 | |
| 200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
| 400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
| 600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
| 800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
所得が高いほど、節税額も多くなることが分かります。
このシミュレーションを参考に、自分の状況に合った掛金を設定することが重要です。
小規模企業共済は節税効果がないと言われる理由
小規模企業共済には多くのメリットがありますが、一部で節税効果が薄いとされる理由も存在します。
・所得が低い場合
・共済金の受取時に税金がかかる
・早期解約は元本割れする
・社会保険料の負担が増える場合がある
所得が低い場合
所得が低い場合、所得税率も低くなるため、掛金を積み立てた際の節税効果が小さくなります。
例えば、年収300万円の方と年収1,000万円の方が同じ70,000円の掛金を支払った場合、節税効果は年収1,000万円の方が高いです。
所得が高い方が、節税効果は高いでしょう。
共済金の受取時に税金がかかる
小規模企業共済の掛金は所得控除の対象ですが、共済金を受け取る際には税金がかかります。
受取時の税率が高い場合、結果的に節税効果が薄れることがあります。
特に、退職金として受け取る場合は、税金の負担を考慮することが大切です。
早期解約は元本割れする
小規模企業共済を早期に解約すると、元本割れのリスクがあります。
掛金を積み立てた分が全て戻ってこない可能性があるため、長期的な視点での運用が求められます。
短期間での解約を考えている方には、あまりおすすめできません。
社会保険料の負担が増える場合がある
役員報酬を増やして、小規模企業共済の掛金を支払う場合は注意が必要です。
役員報酬を増やすことで、社会保険料の負担が増加することが考えられます。
特に、所得が高い場合は、社会保険料の負担が大きくなるため、注意が必要です。
小規模企業共済で節税のメリットをいかすには?

小規模企業共済を効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
・高所得者
・計画的な共済金の受取
高所得者
高所得者にとって、小規模企業共済は活用すべき節税手段です。
所得税率が高いため、掛金を全額控除することで大きな節税効果を得ることができます。
特に、年収が1,000万円を超える方は、積極的に活用することをおすすめします。
計画的な共済金の受取
共済金の受け取りを計画的に行うことで、税金の負担を軽減することが可能です。
受け取り時の税率を考慮し、適切なタイミングで受け取りましょう。
小規模企業共済の活用で注意すべきポイント
小規模企業共済を活用する際に注意すべきポイントを解説します。
・役員報酬が増えると社会保険料も増える
・金融期間からの借入金を活用している場合
役員報酬が増えると社会保険料も増える
小規模企業共済に加入することで、役員報酬を増やすことが可能ですが、その分社会保険料の負担も増加します。
特に、役員報酬が高い場合、社会保険料が大きな負担になります。
そのため、報酬の設定は慎重に行いましょう。
金融機関からの借入金を活用している場合
小規模企業共済を利用する際、金融機関からの借入金を活用している場合は注意が必要です。
借入金の金利負担が節税効果を薄める可能性があるでしょう。
借入金がある場合は、小規模企業共済に加入する前に返済することをおすすめします。
まとめ
小規模企業共済は、将来の備えと節税対策を同時に行える優れた制度です。
特に高所得者にとっては、掛金を全額控除できるため、大きな節税効果が期待できるでしょう。
しかし、所得が低い場合や受取時の税金、早期解約のリスクなど、注意すべき点も多く存在します。
これらを理解し、計画的に活用することで、より効果的な節税対策を実現できます。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。