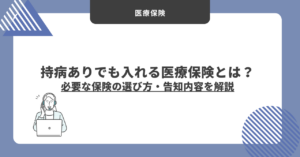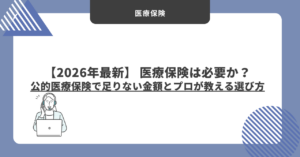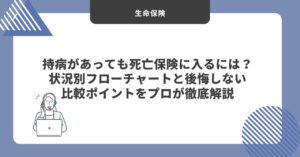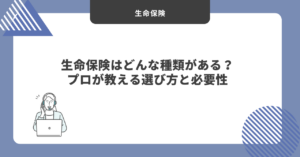小規模企業共済は前納できる?
小規模企業共済で前納をするメリットを知りたい。
小規模企業共済で前納をしようか迷っている個人事業主やフリーランスの方もいるでしょう。
今回は、小規模企業共済の前納について解説します。
この記事を読んだあなたは、前納する場合のメリットや注意点について理解できるでしょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、主に個人事業主や小規模企業の経営者を対象とした共済制度です。
将来の退職金を準備するための制度で、掛金を積み立てることで、万が一の際に共済金(退職金)を受け取ることができます。
この制度は、税制上の優遇措置があり、掛金全額が所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。
また、共済金の受取時にも税負担が軽減されるため、経営者にとって非常に良い制度です。
小規模企業共済の前納とは?
小規模企業共済の前納とは、将来の掛金をあらかじめまとめて支払うことを指します。
通常、掛金は毎月支払う必要がありますが、前納を利用することで一定の割引が適用される「前納減額金」を受け取ることができます。
前納を行うことで、毎月の支払いの手間を省くことができ、資金管理が簡素化にも繋がるでしょう。
小規模企業共済を前納するメリット

小規模企業共済を前納するメリットを解説します。
前納減額金が受け取れる
前納を行うことで、掛金の0.09%が減額金として還付されます。
前納減額金=月額掛金×0.0009×前納月数の累計
月額50,000円で11ヶ月分前納する場合
50,000円×0.0009×66=2,970円
前納月数の累計が11ヶ月の場合、1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66で、66になります。
前納をすることで、実質的に掛金が割引される形となり、経済的なメリットが得られます。
所得控除額が増える
前納を行うことで、その年の所得控除額が増加します。
通常、掛金は毎月支払うため、控除額も月ごとに分散されますが前納を利用することで、最大24カ月分の掛金を一度に控除対象にすることができます。
税負担を軽減し、手元に残る資金を増やすことが可能です。
特に、利益が出ている年に前納を行うことで、より大きな節税効果が期待できるでしょう。
口座振替の手間が減る
毎月の掛金を口座振替で支払う場合、手続きや残高確認が必要ですが、前納を行うことでその手間が省けます。
一度の手続きで済むため、忙しい経営者にとって、このような手間を減らすことは大きなメリットです。
小規模企業共済を前納する場合の注意点
小規模企業共済を前納する場合の注意点を解説します。
・翌年以降の所得控除が減る
・11月以降は「現金あり」で申し込みをする
・口座の残高不足に注意
翌年以降の所得控除が減る
前納を行うと、その年の所得控除が増える一方で、翌年以降の控除額が減少する可能性があります。
これは、前納した分が翌年の控除対象から外れるためです。
前納を行う際は、将来の資金計画をしっかりと考慮する必要があります。
11月以降は「現金あり」で申し込みをする
掛金の支払いは、「現金あり」か「現金なし」で申し込みが可能です。
前納を希望する場合、特に11月以降は「現金あり」での申し込みをするように注意しましょう。
「現金あり」で加入をすることで、年内に現金で掛金を支払うため、全額が控除の対象となります。
しかし、「現金なし」で加入をしてしまうと、初回の口座振替が翌年になり年内に掛金の支払いが完了しないため、翌年の控除対象となってしまいます。
11月以降に前納をする場合は、特に注意が必要です。
口座の残高不足に注意
前納を行う際には、口座の残高不足に注意が必要です。
万が一、口座の残高不足で引き落としが出来なかった場合、その年の控除は受けられません。
必ず事前に口座の残高を確認し、余裕を持った資金管理を心がけましょう。
小規模企業共済の前納方法
小規模企業共済の前納方法は比較的簡単です。
中小機構の公式サイトから「一括納付申請書」をダウンロードして準備しましょう。
必要事項を記入します。
直接、窓口に持っていき、確認印を押印してもらいましょう。
商工会や金融機関で取り扱いが可能ですが、事前に取り扱いをしているか確認することをおすすめします。
確認印があることを確認して、書類を中小機構へ送付します。
手続きが完了すると、「掛金の請求についてのお知らせ」が届きます。
具体的な手続きについては、共済の窓口や公式サイトで確認することをおすすめします。
まとめ
小規模企業共済の前納制度は、前納減額金や所得控除の増加、手間の軽減など、多くのメリットがあります。
ただし、注意点もあるため、計画的に利用することが重要です。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。