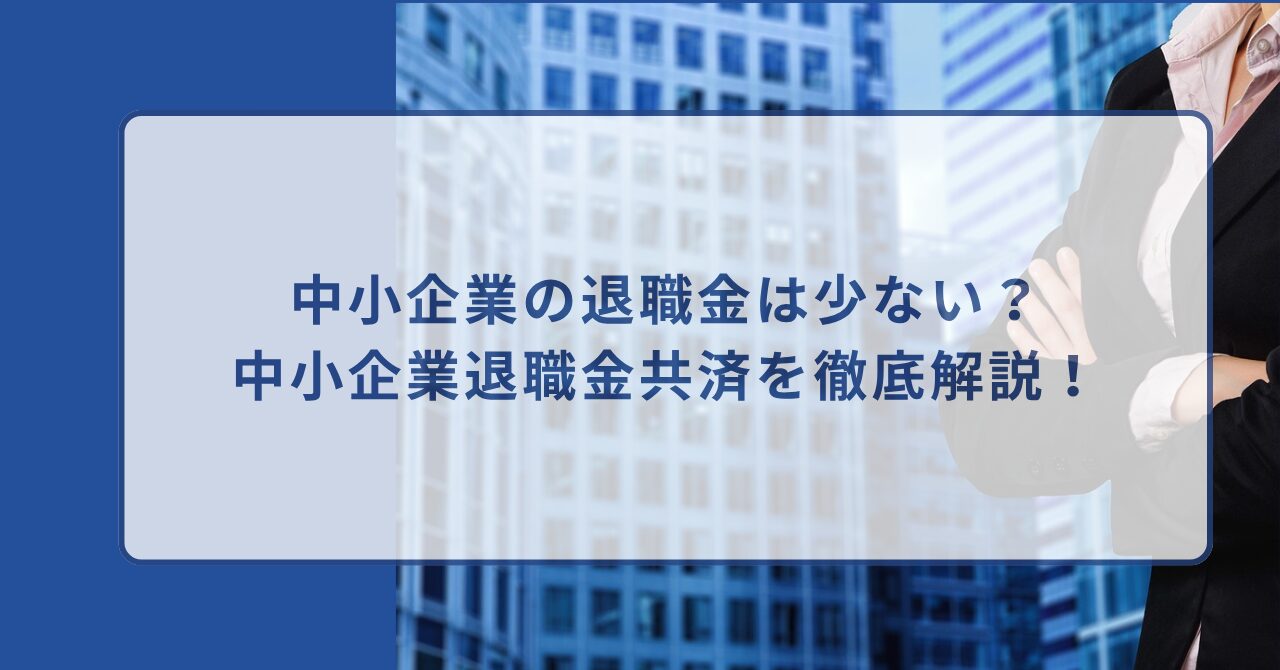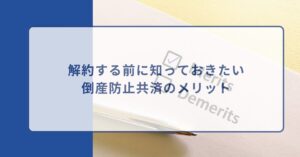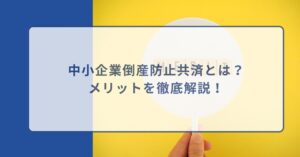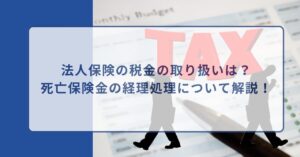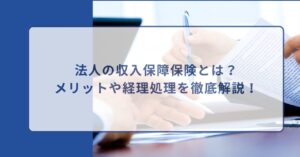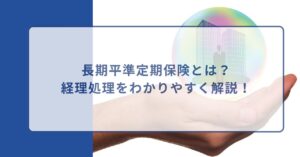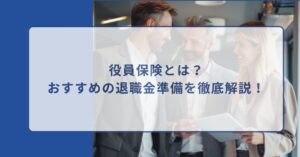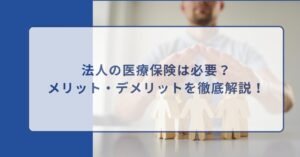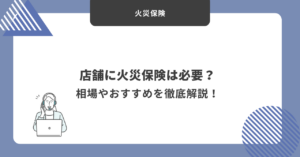中小企業の退職金は少ないのかな?
退職金の計算方法や金額が知りたい。
定年が近づき老後の生活が不安に感じる方も少なくないでしょう。
今回は、中小企業退職金共済や退職金について詳しく解説します。
この記事を読んだあなたは、退職金制度が理解できるでしょう。
中小企業の退職金の平均相場は?
中小企業における退職金の平均相場は、企業の規模や業種、地域によって異なりますが、一般的には大企業に比べて低い傾向があります。
退職金の平均
中小企業の退職金の平均は、企業の業種や地域によって異なりますが、東京都産業労働局1の調査によると1,000万円程度です。
高卒で定年まで勤めた場合:約974万円
大卒で定年まで勤めた場合:約1,149万円
業種別の退職金の平均2は下記の表の通りです。
| 業種 | 高卒 | 大卒 |
|---|---|---|
| 建設業 | 991万円 | 929万円 |
| 製造業 | 1,027万円 | 1,107万円 |
| 運輸業・郵便業 | 886万円 | 938万円 |
| 卸売業・小売業 | 880万円 | 1,239万円 |
| 金融業・保険業 | 1,497万円 | 1,940万円 |
特に製造業や金融業・保険業では、退職金が高めに設定されることが多いです。
また、退職金の額は企業の業績や従業員の勤続年数にも影響されるため、企業ごとの状況を考慮する必要があります。
退職金の計算方法
退職金の計算方法は、企業によって異なりますが、一般的には下記のような式で算出されます。
・定額制
・基本給連動型
定額制は、基本給などは関係なく勤続年数で退職金が決まっている方式です。
勤続年数が長いほど、退職金の額は多くなります。
基本給連動型は、基本給と勤続年数による支給率、退職事由によって計算が異なります。
退職金=基本給×支給率×退職事由係数
勤続年数が30年で支給率が15.0、基本給50万円、自己都合退職の係数0.8の場合、50万円×15.0×0.8=600万円となります。
この倍率は、企業の規定や業種によって異なります。
退職金の計算方法を理解することで、自分の退職金を予測しやすくなるため知っておくと良いでしょう。
退職金は勤務年数によって違う?
一般的に、勤続年数が長いほど退職金は増加します。
勤務年数ごとの退職金の平均を見ていきます。
勤務年数40年の場合の平均
勤務年数が40年の場合、退職金の平均は約800万円から1,200万円程度とされています。
これは、長年にわたる貢献が評価されるため、退職金も高額になる傾向があるからです。
特に、企業の業績が良い場合や、退職金倍率が高い企業では、さらに高額になることもあります。
勤務年数30年の場合の平均
勤務年数が30年の場合、退職金の平均は約600万円から900万円程度です。
40年勤務に比べると若干低くなりますが、それでも十分な額といえるでしょう。
この段階でも、企業の業績や退職金制度の内容によって差が出ることがあります。
勤務年数20年の場合の平均
勤務年数が20年の場合、退職金の平均は約400万円から600万円程度です。
これは、企業が従業員の貢献を評価する一方で、まだ長期的な雇用に対するインセンティブが少ないためです。
そのため、20年勤務の場合は、退職金の額に対して不満を持つこともあるかもしれません。
中小企業退職金共済とは?

中小企業退職金共済制度(中退共)は、独自に退職金制度を設けることが難しい中小企業のために、国が支援する制度です。
この制度を利用することで、中小企業でも大企業と同様の退職金を支払うことが可能になります。
中小企業退職金共済の対象は?
対象となるのは、中小企業の正社員・パート・アルバイトを含むすべての従業員です。
ただし、経営者本人や役員は原則として対象外です。
また、法人だけでなく、個人事業主も加入できます。
加入できる条件は?
中小企業退職金共済に加入するための条件3は、業種ごとに基準が異なります。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業など | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
掛け金はいくらから?
中小企業退職金共済の掛け金は、月額5,000円から30,000円まで設定可能です。
掛け金は、企業の経済状況に応じて柔軟に選択できるため、負担を軽減しながら退職金制度を整えることができます。
また、掛け金は全額が経費として計上できるため、税務上のメリットもあります。
中小企業退職金共済の税務上の取扱いは?
中小企業退職金共済は、企業が支払う掛け金が全額損金として認められる制度です。
節税効果が高い退職金制度として中小企業に人気があります。
また、受け取る側(従業員)にも退職所得控除などの税制優遇があります。
経費にできる?
中小企業退職金共済の掛け金は、全額が経費として計上できます。
・法人の場合:損金扱い
・個人事業主の場合:必要経費扱い
特に、退職金制度を持たない企業にとっては、経費として計上できることが大きなメリットとなります。
勘定科目は?
中小企業退職金共済の掛け金は、「福利厚生費」として計上されることが一般的です。
しかし、会社独自で「退職金共済掛金」などの科目を設けても問題ありません。
適切な勘定科目を選ぶことで、税務上のトラブルを避けることができます。
確定申告は必要?
従業員が退職金を受け取る際は、「退職所得」として課税対象になります。
退職所得控除が大きいため、ほとんどの場合は非課税またはごく少額の課税にとどまります。
退職金受取時は、勤労者退職金共済機構が源泉徴収してくれるため、原則として個人で確定申告は不要です。
取り扱いが気になる方は、税理士などに相談することをおすすめします。
まとめ
中小企業における退職金制度は、従業員のモチベーションを高める重要な要素です。
中小企業退職金共済制度を利用することで、企業は退職金制度を整えやすくなります。
退職金の平均相場や計算方法、勤務年数による違い、税務上の取り扱いについて知ることが大切です。
脚注
- 東京都産業労働局_中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)_Ⅱ調査結果の概要_モデル退職金 ↩︎
- 東京都産業労働局_中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)_Ⅲ集計表_モデル退職金 ↩︎
- 中小企業退職金共済事業本部_加入の条件 ↩︎
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。