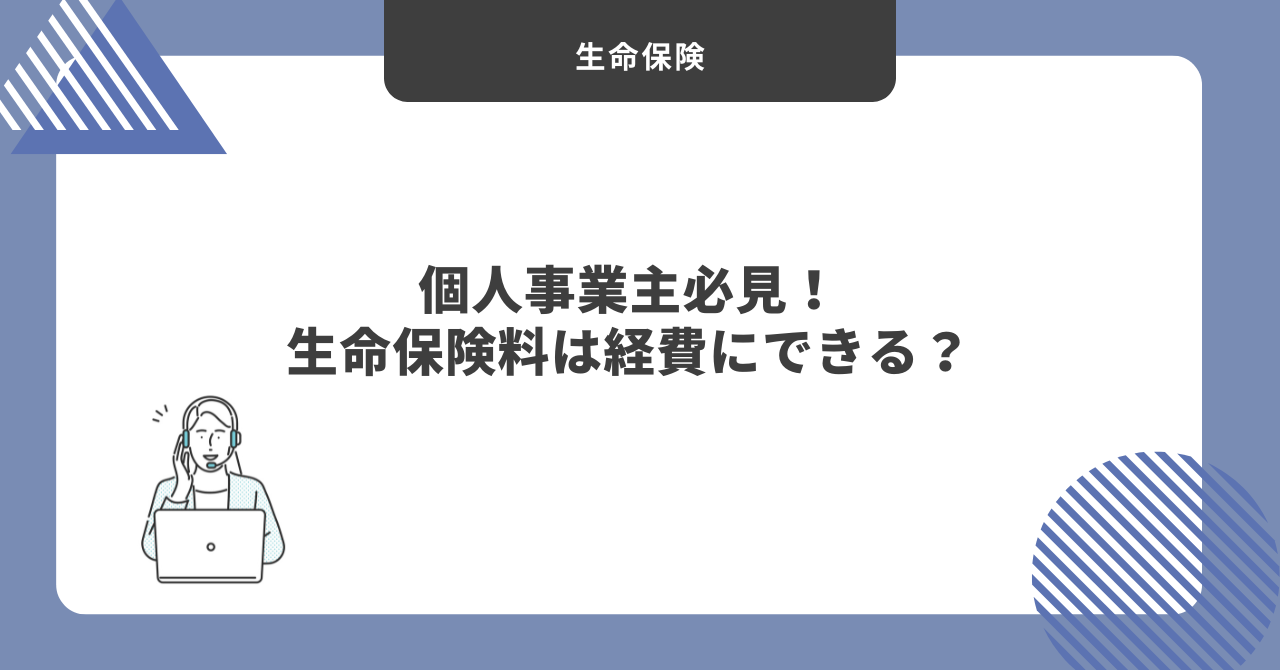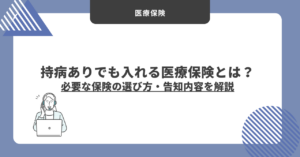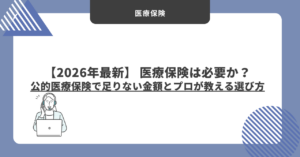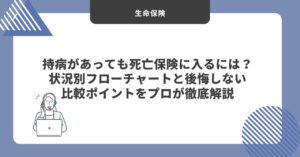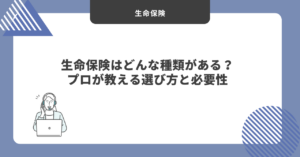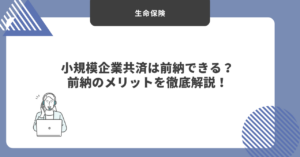加入している生命保険の保険料は経費にできるのかな?
経費に計上できる保険を知りたい。
個人事業主の場合、自身や従業員、事務所などに保険をかけているケースも少なくありません。
どの保険料が経費として計上できるのかいまいち分からない方も少なくないでしょう。
今回は、個人事業主が経費として計上できる生命保険料について解説します。
この記事を読んだあなたは、個人事業主が経費にできる保険料とできない保険料について理解することができるでしょう。
個人事業主が経費にできる保険は?
個人事業主が経費にできる保険には、いくつかの種類があります。
下記の保険は、事業運営に直接関連しているため、経費として計上することが可能です。
・火災保険
・地震保険
・自動車保険
・従業員の保険
火災保険
火災保険は、事業用の建物や設備を保護するための保険です。
万が一の火災や災害に備えるため、経費として計上することができます。
「損害保険料」・「保険料」の勘定科目で計上します。
事業に必要不可欠な保険であるため、税務上も認められている保険です。
地震保険
地震保険も、事業用の資産を守るために重要な保険です。
特に地震が多い地域では、事業の継続性を確保するために加入が推奨されます。
こちらも「損害保険料」・「保険料」経費として計上可能です。
自動車保険
事業用の車両に対する自動車保険も経費に含まれます。
業務で使用する車両が事故に遭った場合のリスクを軽減するため、必要な保険と言えるでしょう。
業務に関連する使用が明確であれば、「損害保険料」・「車両費」の経費として認められます。
従業員の保険
従業員のために加入する保険は経費に計上できます。
福利厚生の一環としての生命保険や医療保険も「福利厚生費」として計上が可能です。
従業員の福利厚生を充実させることは、事業の成長にも繋がる大切なことでしょう。
個人事業主が経費にできない保険は?
反対に、個人事業主が経費にできない保険も存在します。
下記の保険は、事業とは直接関係がないため、経費として計上することはできません。
・個人事業主の生命保険
・個人事業主の保険
・国民健康保険・国民年金保険
個人事業主の生命保険
個人事業主自身が加入する生命保険は、経費として計上できません。
生命保険が個人の生活を保障するものであり、事業の運営には直接関与しないためです。
しかし、社会保険料控除として所得控除は可能のため、申告を忘れないようにしましょう。
個人事業主の保険
個人事業主が私的に加入した地震保険や火災保険などの保険も同様に経費にはなりません。
事業資金から支払った場合でも、個人の保険として扱われるため、経費計上はできないため注意が必要です。
国民健康保険・国民年金保険
国民健康保険や国民年金保険も、個人の生活に関わる保険であり、経費としては認められません。
こちらは所得控除の対象となりますが、経費計上はできない点に注意が必要です。
生命保険料を経費に計上する場合の注意点

生命保険料を経費に計上する際には、いくつかの注意点があります。
・必要な書類を揃える
・事業とプライベートを按分する
これらを理解しておくことで、適切に経費処理を行うことができるでしょう。
必要な書類を揃える
経費として計上するためには、必要な書類を揃えることが重要です。
事業に関する支出であると証明するために、領収書は必ず残しておくようにしましょう。
また、保険契約書や支払い証明書など、税務署から求められる書類を準備することでスムーズに処理をすることが可能です。
事業とプライベートを按分する
生命保険料が事業とプライベートの両方に関連する場合、按分が必要です。
事業に関連する部分のみを経費として計上し、プライベート部分は除外する必要があります。
これを適切に行わないと、税務調査が入った場合に指摘される可能性があるため注意が必要です。
生命保険料を経費に計上する場合のポイント
生命保険料を経費に計上する際のポイントについて紹介します。
毎年支払う場合
毎年支払う生命保険料については、支払いが発生した年に経費として計上できます。
年度ごとにしっかりと記録を残しておくことが大切です。
複数年の分をまとめて支払う場合
複数年分の生命保険料をまとめて支払った場合、その全額を一度に経費として計上することはできません。
期間ごとに経費計上する必要があります。
個人事業主が経費にできない保険料は控除の対象
経費にできない保険料でも、控除の対象となるものがあり、税金の負担を軽減することが可能です。
社会保険料控除
社会保険料控除は、国民健康保険や年金保険など、社会保険に関連する支出を控除できる制度です。
全額が控除の対象となるため、税の負担を軽減できます。
生命保険料控除
生命保険料控除は、個人が支払った生命保険料に対して適用される控除です。
生命保険料控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払額の全額 |
| 25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払額の全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払額の全額 |
| 20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払額の全額 |
| 12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度と旧制度の両方に加入している場合
新制度と旧制度の両方に加入している場合、旧制度の年間保険料が60,000円を超えているかで控除額が決まります。
旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていれば、旧制度のみで控除額を計算します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えている場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:50,000円
・住民税:35,000円
旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていない場合は、新制度と旧制度のそれぞれで控除額を計算して合計します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えていない場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:40,000円
・住民税:28,000円
具体的な控除額や条件については、税務署や税理士などに相談することをおすすめします。
まとめ
個人事業主が生命保険料を経費に計上する際には、経費にできる保険とできない保険をしっかりと理解することが重要です。
また、必要な書類や按分の方法についても注意が必要になります。
正しい経費処理を行い、税金対策を行いましょう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。