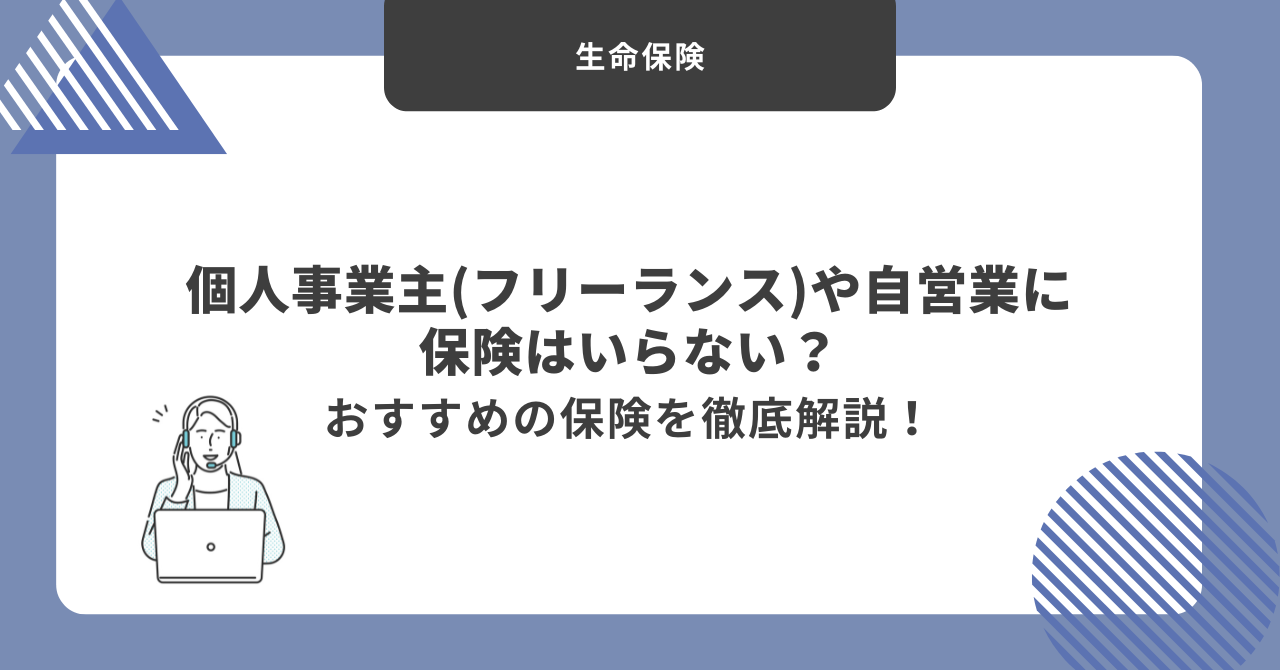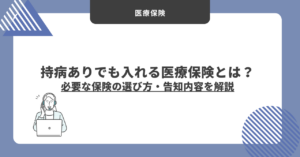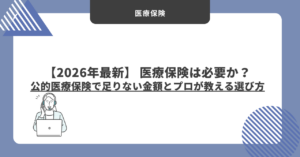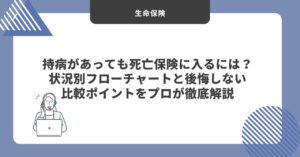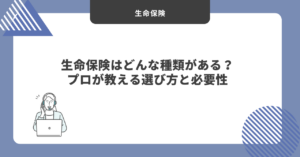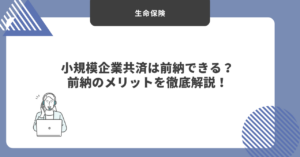個人事業主や自営業は、どんな保険が必要なのかな?
会社員ではないフリーランスが加入すべきおすすめの保険が知りたい。
個人事業主の場合、リスクを自分で補おうと考える方も少なくないでしょう。
しかし、どのような保険が適しているのか分からない方も多いです。
今回は、個人事業主やフリーランス、自営業におすすめの生命保険を解説します。
この記事を読んだあなたは、個人事業主として働く場合の保険の必要性について理解することができるでしょう。
個人事業主・フリーランス・自営業とは?
まずは、個人事業主・フリーランス・自営業とは、どのような人のことを指すのかを紹介します。
個人事業主
個人事業主とは、法人を設立せずに自ら事業を営む人のことです。
税務署に開業届を提出し、自分の名前または屋号で事業を営む個人を指します。
自由な働き方を求める人々が多く、特定の業種に限らず、様々な分野で活動していることが多いです。
しかし、個人事業主は収入が不安定な場合も多く、リスク管理が重要となります。
フリーランス
フリーランスは、特定の雇用契約に縛られず、自由に仕事を受ける形態を指します。
クリエイティブな職業やIT関連の仕事が多く、プロジェクトごとに契約を結ぶことが一般的です。
フリーランスも収入が変動しやすいため、リスク管理が重要となります。
自営業
自営業は、個人事業主と似ていますが、店舗を持つなど、より具体的な形態を指すことが多いです。
飲食店や小売業など、顧客と直接接するビジネスが多く、経営リスクも伴います。
自営業者も、保険によるリスクヘッジが求められるでしょう。
個人事業主・フリーランス・自営業と会社員の違い
会社員は健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保障が手厚く、病気やケガで働けない場合も一定の保障があります。
一方、個人事業主やフリーランス、自営業者は、会社員とは異なり安定した給与や福利厚生がありません。
収入が不安定であるため、病気や事故にあった場合、収入がなくなるリスクが高くなります。
また、会社員とは年金や保険の制度も異なるため、自己責任でのリスク管理が必要でしょう。
| 個人事業主・フリーランス・自営業 | 会社員 | |
|---|---|---|
| 公的医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険 |
| 公的年金 | 国民年金 | 国民年金+厚生年金 |
| 労働保険 | なし | 労災保険+雇用保険 |
会社員の健康保険や厚生年金は、保険料負担が会社と折半で支払われるため、個人負担が少ないことや個人事業主などに比べて補償内容が充実していることが魅力的です。
会社員の場合は、何かあった時でも保障がしっかりしていますが、個人事業主・フリーランス・自営業は最低限の保障しかないため、ご自身でしっかりと万が一に備える必要があります。
個人事業主・フリーランス・自営業の保険の必要性
個人事業主やフリーランス、自営業者は、会社員に比べて公的な保障が少ないため、保険の必要性が高まります。
特に、下記のような理由から保険の加入を検討することが重要です。
傷病手当がない
個人事業主などが加入する国民健康保険と、会社員が加入する健康保険は基本的には保障内容は同じです。
しかし、会社員が加入する健康保険では傷病手当を受け取ることができますが、個人事業主が加入する国民健康保険にはその制度がありません。
傷病手当とは、病気やけがにより勤務ができなくなった場合に、健康保険から給付金が支給され、働けない間の生活を支えるために設けられた制度です。
病気やけがにより会社を休み連続して4日以上仕事に就けない場合に、4日目から最長1年6か月間支給されます。
支給額は標準報酬日額のおよそ3分の2です。
傷病手当のない個人事業主は、病気やケガで働けなくなった場合、収入が途絶えるリスクが高いです。
そのため、医療保険や就業不能保険が必要です。
老齢年金が少ない
個人事業主やフリーランスは国民年金に加入し、会社員は国民年金と厚生年金に加入します。
そのため、会社員は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できますが、個人事業主は老齢基礎年金のみしか受給できません。
個人事業主は、老後に受け取れる年金が会社員に比べると少なくなります。
厚生労働省の調査1によると、令和5年度の平均受給額は下記の通りです。
| 国民年金 | 厚生年金 | |
|---|---|---|
| 令和3年 | 56,479円 | 145,665円 |
| 令和4年 | 56,428円 | 144,982円 |
| 令和5年 | 57,700円 | 147,360円 |
個人事業主などが受け取る国民年金は、会社員が受け取れる厚生年金の1/3程度となっています。
そのため、老後の生活資金を確保するためには、個人年金保険などの活用が求められます。
遺族年金・障害年金が少ない
個人事業主やフリーランス、自営業者は、老齢年金だけではなく、万が一のときに受け取れる遺族年金や障害年金も、会社員や公務員に比べて少ないです。
家族の生計を支えていた人が亡くなったときに、残された配偶者や子どもが受け取れる年金
病気やけがで生活や仕事に大きな制限が出たときに、本人が受け取れる年金
生命保険や障害保険を検討することで、家族や自身の生活を守ることができます。
個人事業主・フリーランス・自営業が備えるべきリスク

個人事業主やフリーランス、自営業者は、下記のようなリスクに備える必要があります。
・死亡のリスク
・病気やケガのリスク
・働けない場合のリスク
・老後のリスク
死亡リスク
遺された家族の生活を支えるために、死亡保障は必要です。
特に子どもがいる個人事業主の方は、残された家族が生活に困らないように死亡した場合の保障を手厚くしておく必要があります。
それ以外にも、死亡した場合には葬儀費用やお墓の費用が必要になるため、お金が必要になります。
家族の生活を守るためにも、適切な保障額を設定することが重要です。
病気やケガのリスク
入院や手術にかかる医療費は高額になることがあるため、医療保険で備えると安心です。
自営業やフリーランスの場合、入院で働けないと収入が不安定になるため、治療費や生活費をカバーできる保険に加入する必要があります。
働けない場合のリスク
個人事業主は会社員と違って、働けない=収入ゼロになる可能性が高いです。
働けない状況に備えるためには、所得補償保険や収入保障保険がおすすめです。
これにより、収入が途絶えた際の生活を支えることができます。
老後のリスク
個人事業主は、会社員に比べて貰える年金額が少ないため、老後の保障が手薄です。
老齢基礎年金だけでは、生活費が不足する可能性が高いため、年金だけで生活をするのは厳しいでしょう。
そのため、個人年金保険や資産運用での備えが必要です。
早めに準備を始めることで、安心した老後を迎えることができるでしょう。
個人事業主・フリーランス・自営業におすすめの保険
個人事業主やフリーランス、自営業者におすすめの保険を紹介します。
それぞれの保険の特徴を理解し、自分に合った保険を選びましょう。
医療保険
医療保険は、入院や手術に備えるための保険です。
病気やケガによる治療費をカバーし、安心して治療に専念できます。
入院や手術の自己負担を軽減できることが特徴です。
終身保険
終身保険は、死亡時に保障が受けられる保険です。
遺された家族の生活を守るために、適切な保障額を設定することが重要となります。
個人年金保険
個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための保険です。
早めに加入することで、安心した老後を迎えることができます。
就業不能保険
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合に収入を補償する保険です。
収入が途絶えた際の生活を支えるために重要となります。
所得補償保険
所得補償保険は、働けない場合に収入を補償する保険です。
生活費をカバーするために、加入を検討しましょう。
収入保障保険
収入保障保険は、一定期間の収入を保障する保険です。
特に、家族を養う立場の方は、加入することで安心を得られるでしょう。
個人事業主・フリーランス・自営業が経費として扱える保険は?
個人事業主やフリーランス、自営業者が経費として扱える保険について解説します。
経費として扱える保険料
経費として扱える保険であるかは、事業に必要な保険であるかどうかで決まります。
業務上のリスクに備えるための保険は経費として計上可能です。
・仕事で使う車の自動車保険
・事務所として使っている建物の火災保険・地震保険
・従業員の生命保険・傷害保険
経費対象外の保険料
個人的な保険料や、事業に関連しない保険は経費として扱えません。
・自身が被保険者となる生命保険
・自身や専従者の傷害保険
・自身や専従者の国民健康保険・年金
経費計上の際は、間違った取り扱いをしないために注意が必要です。
個人事業主・フリーランス・自営業は保険料控除の対象?
個人事業主やフリーランス、自営業者は、生命保険に加入することで保険料控除の対象となります。
生命保険や医療保険の保険料を控除することで、税金の負担を軽減できます。
生命保険料控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払額の全額 |
| 25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払額の全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払額の全額 |
| 20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払額の全額 |
| 12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度と旧制度の両方に加入している場合
新制度と旧制度の両方に加入している場合、旧制度の年間保険料が60,000円を超えているかで控除額が決まります。
旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていれば、旧制度のみで控除額を計算します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えている場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:50,000円
・住民税:35,000円
旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていない場合は、新制度と旧制度のそれぞれで控除額を計算して合計します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えていない場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:40,000円
・住民税:28,000円
具体的な控除額や条件については、税務署や税理士などに相談することをおすすめします。
まとめ
個人事業主やフリーランス、自営業は会社員に比べて公的保障が少ない分、自ら保険で備えることが重要です。
医療・死亡・就業不能・老後資金といったリスクに合わせて、必要な保険を組み合わせて検討しましょう。
保険の選び方や活用法を理解し、将来に備えることが大切です。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。