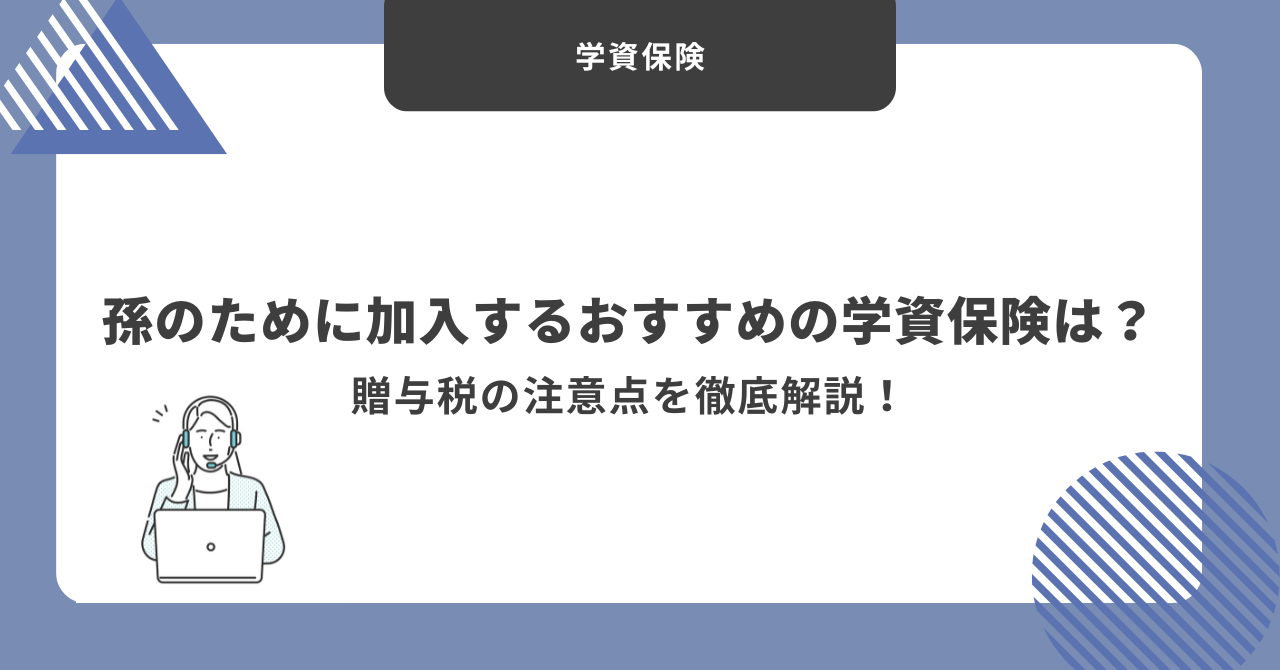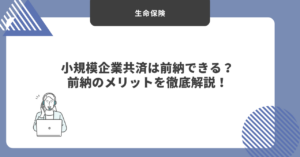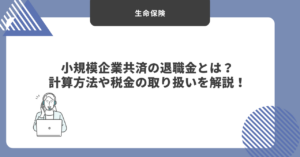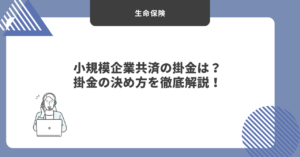孫ために、学資保険に加入したいけど祖父母が契約できるのかな?
学資保険でも、贈与税の対象になるって本当?
親だけではなく、祖父母も孫の将来のために学資保険に加入して入学祝いや教育資金の援助をしたいと考える方は少なくないでしょう。
今回は、祖父母が孫のために加入する学資保険について分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、祖父母が学資保険に加入する場合の税金や注意点について理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険です。
主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。
契約者(親・祖父母)が保険料を支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。
また、契約者に万が一のことがあった場合でも、その後の保険料の支払いが免除され、満期時には予定通りの給付金が支払われる仕組みです。
子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。
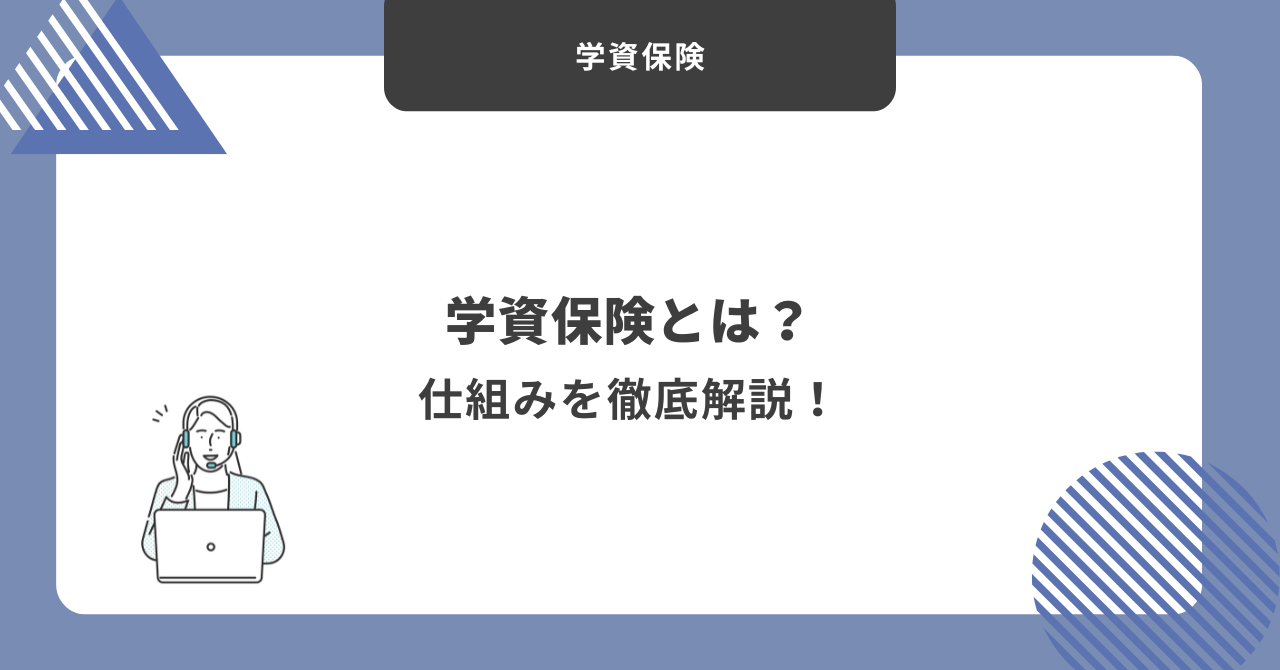
孫のために学資保険に加入できる?
祖父母が可愛いお孫さんのために、教育資金の準備として学資保険を検討するケースは多いでしょう。
孫を被保険者として、祖父母が契約者となって学資保険に加入することは可能です。
しかし、契約にはいくつかの条件や注意点があるため、事前にしっかりと確認する必要があります。
学資保険は基本的には親が契約者となる場合が多いですが、ほとんどの保険会社では契約者は親だけでなく、祖父母でも良いとされています。
契約者が保険料を支払い、万が一の際には教育資金が保障されるという仕組みは同じです。
お孫さんが小学校・中学校・高校・大学へと進学する際のまとまった教育に関する出費に備える方法として、学資保険はおすすめです。
孫のために学資保険に加入する場合の注意点

祖父母が孫のために学資保険に加入することはできますが、いくつか注意点があるため紹介します。
・年齢や健康状態によって加入できない場合がある
・保険料が高くなる可能性がある
・親権者の同意が必要
年齢や健康状態によって加入できない場合がある
学資保険では、契約者が死亡や高度障害となった場合の免除制度が付いていることが多いため、契約者の年齢や健康状態が審査の対象になります。
一般的に、契約者の年齢上限は60歳〜65歳までとしている保険会社が多く、健康診断書や告知書の提出が求められる場合もあります。
そのため、祖父母が孫のために加入を考えている場合は、できるだけ早めに申し込みを行いましょう。
高齢出産家庭の場合は、祖父母の年齢が高齢であれば学資保険に加入できない場合もあります。
また、持病がある場合や通院歴がある方は、審査に通らない可能性もあるため、必ず学資保険に加入できる訳ではないということを覚えておきましょう。
保険料が高くなる可能性がある
保険は、契約者の年齢が高いほど保険料が割高になる傾向があります。
例えば、20代の親が契約する場合と比べて、50代の祖父母が契約する場合では、同じ保障内容でも月々の保険料が高くなります。
保険料の支払い総額や、受け取れる金額とのバランスをよく比較して無理のない学資保険に加入しましょう。
親権者の同意が必要
お孫さんを被保険者とする場合、親権者であるお子さん(お孫さんの父母)の同意が必要になります。
お孫さんと同居している場合、同居している証明が必要になるケースもあります。
未成年を被保険者にする保険契約において、親権者の意思確認が法的に必要とされるためです。
契約時には、保険会社から親権者の同意書や本人確認書類の提出を求められます。
事前に親子間でしっかりと話し合い、スムーズに手続きが進められるようにしておきましょう。
孫のための学資保険!税金はどうなる?
お孫さんのために祖父母が学資保険に加入する場合に注意しなければならないのが「税金」です。
受け取り方法や契約内容によって課税される税金の種類が異なります。
祝い金・満期保険金の受け取り時にかかる税金
学資保険において、祝い金や満期保険金を誰が契約して誰がどのように受け取るかによって課税対象が変わります。
| 契約者と受取人 | 受け取り方 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 契約者と受取人が同じ | 一括 | 所得税(一時所得) |
| 年金 | 所得税(雑所得) | |
| 契約者と受取人が異なる | 一括・年金 | 贈与税 |
よくあるパターンの例は、下記の通りです。
| 一時所得 | 雑所得 | 贈与税 | 贈与税 | |
|---|---|---|---|---|
| 契約者 | 父 | 父 | 祖父 | 祖父 |
| 被保険者 | 子ども | 子ども | 孫 | 孫 |
| 受取人 | 父 | 父 | 孫 | 孫との父 |
| 受け取り方 | 一括 | 年金形式 | – | – |
祖父母が契約した場合にかかる贈与税
契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」が発生するため、祖父母が学資保険を契約し保険金を孫やその親に渡す場合は、贈与税が発生します。
これは、保険金が契約者から受取人への贈与とみなされるからです。
贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して課税されます。
例えば、学資保険の満期金として200万円を一括で孫に渡した場合、差額の90万円に対して贈与税がかかる計算です。
贈与税=(保険金−基礎控除110万円)×税率-控除額
税率は受取額に応じて10%〜55%まで累進課税されます。
しかし、満期金を50万円×4年に分けて孫に渡す場合は、年間110万円を超えないため、他に贈与がなければ贈与税はかかりません。
できるだけ税金がかからないように工夫する必要があります。
祖父母が孫の教育費を負担する方法
税制優遇を受けながらお孫さんの教育費を支援する方法があります。
代表的な3つの方法を紹介します。
・暦年贈与
・教育資金一括贈与
・相続時精算課税制度
暦年贈与
一番一般的な方法が、「暦年贈与」です。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、110万円以下であれば贈与税を非課税にできます。
祖父母から孫へ年間110万円以下の援助であれば、贈与税がかからないので申告も不要です。
定期贈与に注意
しかし、暦年贈与は「定期贈与」とみなされないように注意する必要があります。
定期贈与は、「1,500万円を15回に分けて年間100万円ずつ贈与する」など、元々決めた金額を分割して贈与することです。
この場合は、年間100万円の贈与なので110万円以下に収まっているため、贈与税はかからないと思う方も少なくないでしょう。
しかし、定期贈与とみなされると、年間ではなく総額に対し贈与税がかかることになります。
そのため、1,500万円に対して贈与税がかかるのです。
定期贈与とみなされないためには、贈与契約書を作成しておくなどの対策が必要でしょう。
教育資金一括贈与
教育資金に限っては、1,500万円までの贈与が非課税になる「教育資金一括贈与制度」があります。
教育資金一括贈与の概要は、下記の通りです。
| 対象者 | 30歳未満の子・孫 |
| 対象贈与者 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 非課税限度額 | 子や孫1人あたり1,500万円まで |
| 資金の管理方法 | 銀行や信託銀行など、指定金融機関の専用口座で管理 |
| 使い道 | 学校の授業料、入学金、塾・習い事などの教育費 |
| 証明書の提出 | 教育資金として使ったことを証明する領収書などが必要 |
祖父母が金融機関を通じて、孫名義の口座に一括贈与をして、その口座から教育費を支払うことで贈与税がかからない制度です。
30歳までに使い切らなかった残額に対しては贈与税がかかったり、教育関連での使い道のみ対象など条件があるため注意が必要です。
また、2026年3月末までの期間限定措置となっているので、利用を考えている方は早めに手続きをしましょう。
相続時精算課税制度
最後の方法が、「相続時精算課税制度」です。
これは、2,500万円までの贈与を非課税とし、相続時にまとめて課税される制度です。
相続時精算課税制度の概要は、下記の通りです。
| 対象者 | 18歳以上の子・孫 |
| 対象贈与者 | 60歳以上の両親・祖父母 |
| 非課税限度額 | 1人につき2,500万円まで |
| 課税のタイミング | 贈与者が亡くなった時に相続財産に合算して課税 |
| 申告 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ申告する必要がある |
高額な資金を一度に贈与できたり、教育資金や住宅を購入する資金に使えたり、贈与税の負担を一時的に回避できることがメリットです。
しかし、一度この制度を選択すると暦年贈与による非課税枠は今後使えなくなるという注意点があります。
また、最終的に相続税として課税される可能性もあるため、資産全体の管理をして検討が必要です。
相続対策は家庭によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
学資保険は、親だけではなく祖父母が孫の将来の教育資金のために加入することができます。
しかし、加入条件などがあるため事前に保険会社に確認しましょう。
また、祖父母が孫のために加入した学資保険は、ケースによっては相続税がかかることもあるため、しっかりと保障内容やかかる税金について検討することが大切です。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。