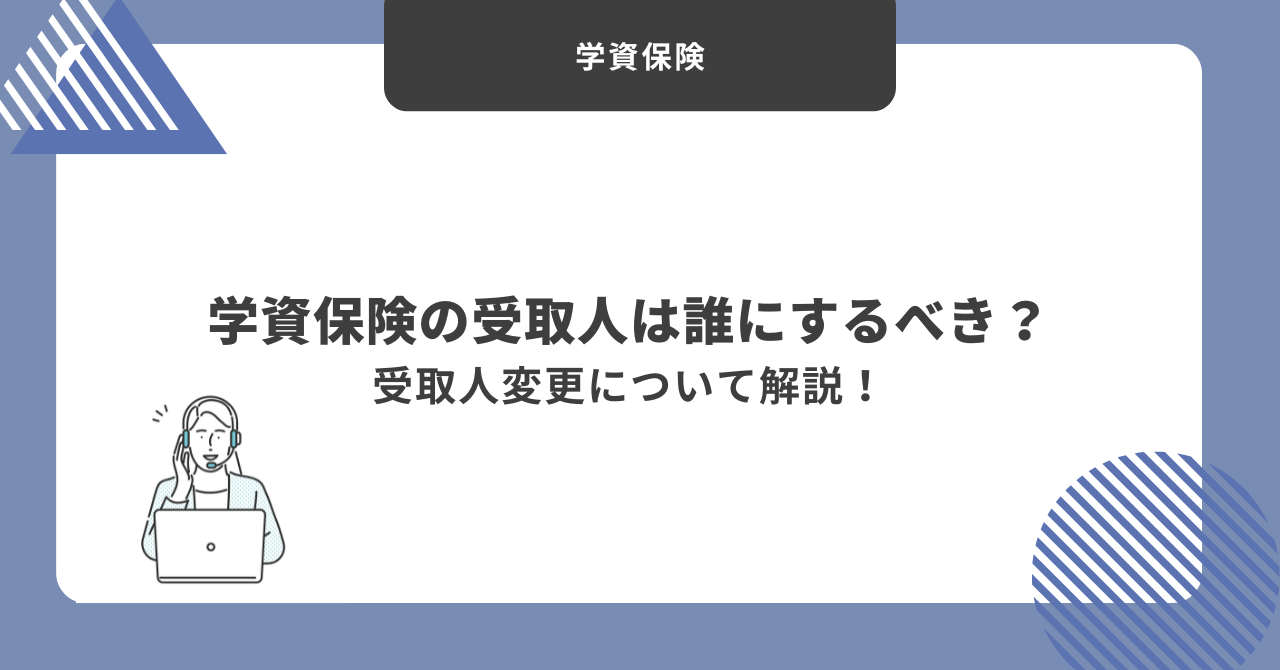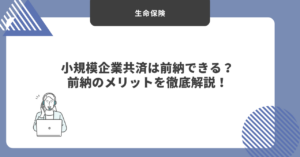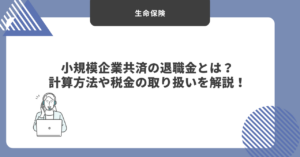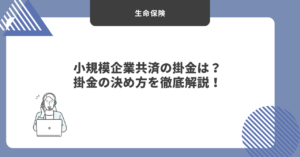学資保険は子どものための保険だから受取人は子どもにするのかな?
学資保険の契約者と受取人を誰に設定しようか迷う。
学資保険の加入を考えている時に、契約者や受取人をどう設定しようか迷われる方も少なくないでしょう。
今回は、学資保険の受取人について分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の受取人の設定と税金との関係について理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険です。
主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。
契約者(親)が保険料を支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。
また、契約者に万が一のことがあった場合でも、その後の保険料の支払いが免除され、満期時には予定通りの給付金が支払われる仕組みです。
子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。
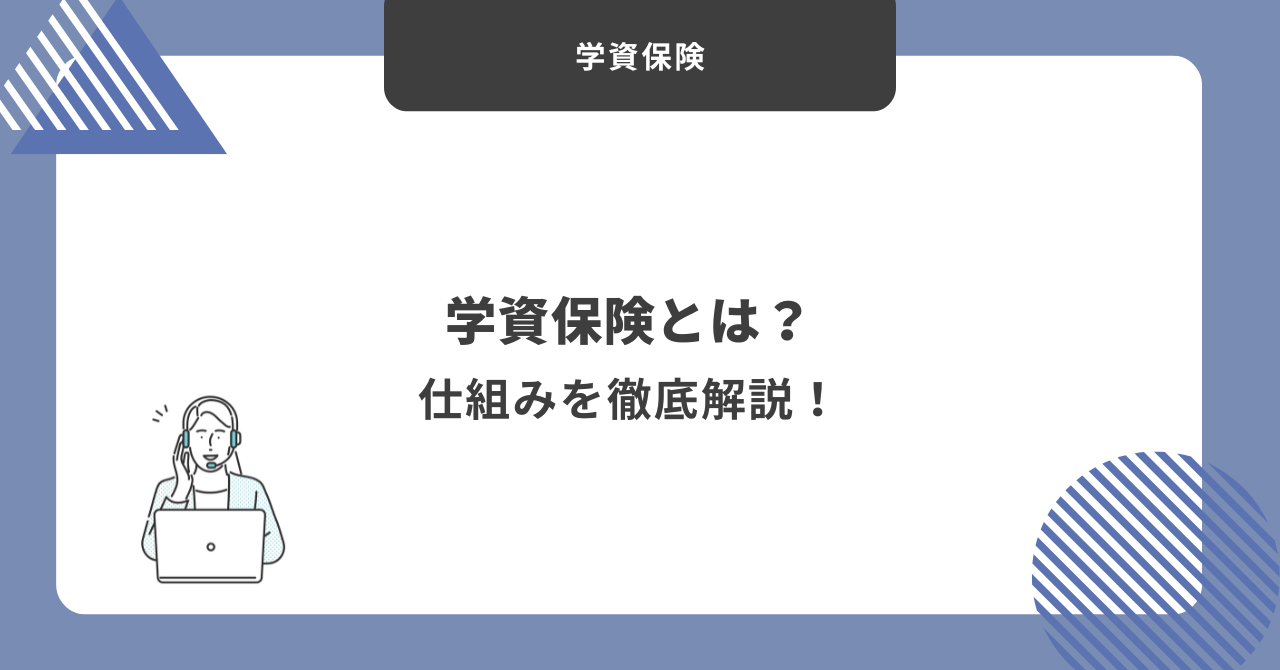
学資保険の契約者・被保険者・受取人とは?
保険には、契約者・被保険者・受取人が関わってきます。
それぞれの役割を理解しておくことが大切です。
学資保険の契約者
契約者とは、学資保険を申し込み保険料を支払う人のことです。
多くの場合、子どもの親が契約者になります。
契約者になれる人は、何親等以内の親族に限られる場合や年齢があり、条件は保険会社によって異なるため確認が必要です。
祖父母が契約者になる場合は、契約者の年齢に上限が定められていることが多いため注意しましょう。
また、契約者には保険内容の変更や解約をする権限があります。
学資保険の被保険者
被保険者は、保険の対象となる人です。
学資保険では通常、子どもが被保険者となります。
学資保険は教育資金に備えることを目的とした保険のため、被保険者の子どもの年齢にも条件があります。
一般的に6歳頃までに加入することが条件となっている場合が多いため、加入する保険会社に確認しましょう。
学資保険の受取人
受取人とは、保険金(満期保険金や祝い金など)を受け取る人のことです。
多くの場合は、契約者と同一人物が受取人になります。
しかし、契約の仕方によっては異なる人にすることも可能です。
受取人を誰に設定するかで、かかる税金の種類が変わるため、しっかりと考えて決めましょう。
学資保険の受取人で税金が変わる

学資保険では、「誰が契約者で、誰が受取人か」によって課税される税金の種類が異なります。
これは非常に重要なポイントです。
| 一時所得 | 雑所得 | 贈与税 | 贈与税 | |
|---|---|---|---|---|
| 契約者 | 父 | 父 | 祖父 | 祖父 |
| 被保険者 | 子ども | 子ども | 孫 | 孫 |
| 受取人 | 父 | 父 | 孫 | 孫との父 |
| 受け取り方 | 一括 | 年金形式 | – | – |
契約者と受取人が同じ
契約者と受取人が同じ場合は、受け取り方によって取り扱いが異なります。
・一括受け取りの場合:一時所得
・年金受け取りの場合:雑所得
契約者と受取人が同じで、満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」として扱われます。
一時所得には50万円の特別控除があり、一定の条件を満たせば課税額を抑えられます。
一時所得 = 保険金 − 支払保険料総額 − 特別控除(最高50万円)
課税対象 = 一時所得 × ½
契約者と受取人が同じで、保険金を年金形式で受け取る場合は「雑所得」として扱われます。
雑所得 = その年に受け取った祝金-その年に受け取った祝金×(支払保険料総額÷祝金総額)
雑所得には特別控除はありません。
一定の要件を満たす給与所得者は雑所得の金額が20万円以下の場合、申告が不要です。
契約者と受取人が違う
契約者と受取人が異なる場合は、「贈与税」が発生する可能性があります。
これは、保険金が契約者から受取人への贈与とみなされるからです。
贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、それを超えると課税対象となります。
贈与税=(保険金−基礎控除110万円)×税率-控除額
契約者と受取人を同じにするケースが多い
学資保険では、「契約者」と「受取人」を同一人物に設定することが多いです。
契約者と受取人が同じである場合は、所得税の対象となります。
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税や相続税の対象になる可能性があります。
一時所得には50万円の特別控除や課税額1/2ルールがあるため、比較的負担が軽く済みます。
そのため、契約者と受取人を同一で契約することが税制上有利です。
ただし、契約者・受取人の職業や意向によってベストな設定は異なります。
各家庭の状況を保険会社や専門家に相談して、一番合った方法で加入することをおすすめします。
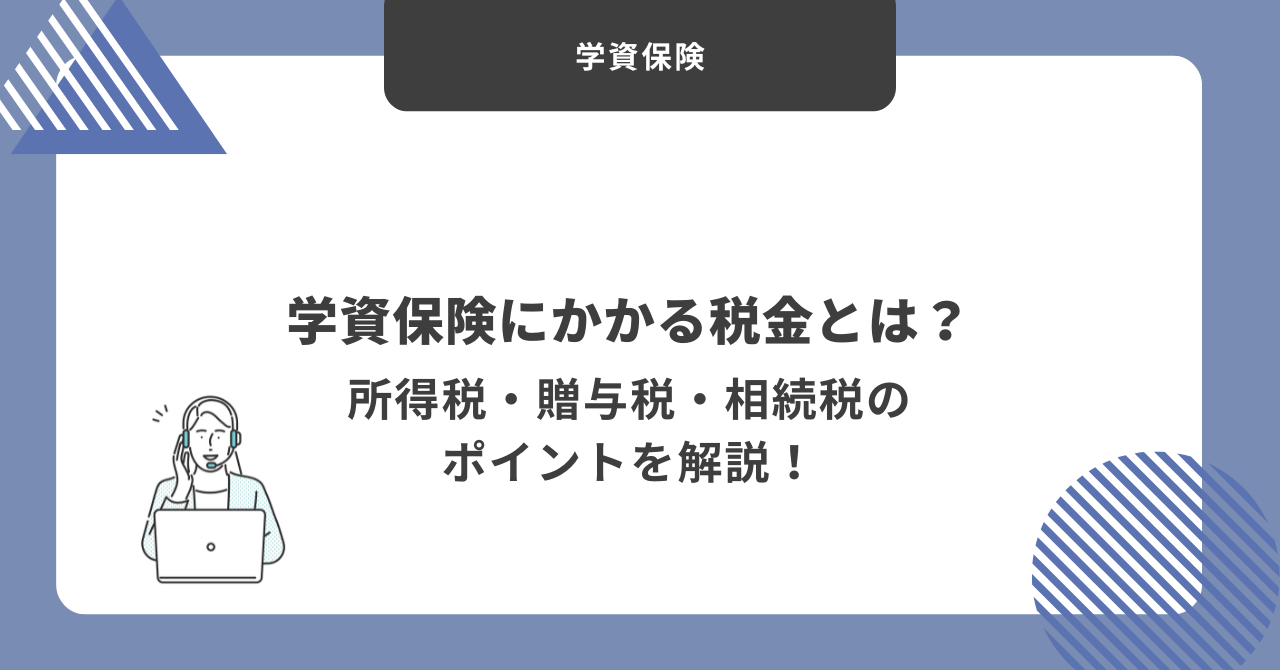
学資保険の受取人を変更することはできる?
学資保険では、受取人を後から変更することが可能です。
さまざまな事情により、受取人を変更する必要が生じるケースも少なくありません。
ここでは変更が可能なタイミングや手続きについて説明します。
受取人の変更はいつでもできる
基本的に、契約者の意思によって受取人はいつでも変更可能です。
変更には、保険会社に申請書類を提出する必要があります。
特別な事情がない限り、いつでも変更手続きは受け付けてもらえます。
契約者保険の署名・捺印が必要な場合が多く、保険会社によっては本人確認書類の提出が求められることもあるでしょう。
また、保険金受取時の課税関係に影響が出る可能性もあるため、注意が必要です。
離婚・受取人が死亡した場合は変更手続きが必要
離婚など家庭環境の変化や、受取人が死亡した場合には、保険会社に申し出て変更の手続きをする必要があります。
放置すると、いざという時に保険金を受け取れないトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
離婚後に元配偶者が受取人のままだと、保険金を受け取るのはその元配偶者になります。
円満離婚や子どもの養育に関して話し合いができている場合は問題ありませんが、そうではない場合は注意が必要でしょう。
また、受取人が亡くなって変更していないと、保険金の支払いがスムーズに進まないことがあります。
受取人が亡くなった場合は、早めに変更手続きをすることをおすすめします。
学資保険の年末調整に受取人は関係する?
学資保険の年末調整では、基本的に受取人は関係しません。
学資保険では多くの場合、「契約者=受取人」で設定されているため、受取人だから年末調整に関係すると思われてる方も少なくないでしょう。
しかし、年末調整で関係してくるのは、契約者(保険料の支払い者)です。
なぜなら、控除対象となる「生命保険料控除」は、実際に保険料を負担している人に適用されるためです。
受取人ではなく、契約者だから保険料の控除を受けるために年末調整が必要となります。
保険金を受け取った場合は、受取人は条件によっては確定申告が必要になるケースがあります。
誰が保険料を支払って、誰が保険金を受け取ったかと、受け取った金額によってかかる税金が異なります。
満期保険金を受け取っても確定申告が不要な場合は、下記の通りです。
例外もあるため、ご自身が受取人の場合で確定申告が必要になるかは、保険会社や専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
学資保険の受取人は契約者との関係によって、保険金を受け取る際の税金が変わってきます。
もし、離婚や受取人が死亡した場合、受取人を変更することはいつでも可能ですが、早めに手続きをすることをおすすめします。
家庭の状況を考えて、受取人を誰にするかをしっかり考えて設定することで将来の安心につながるでしょう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。