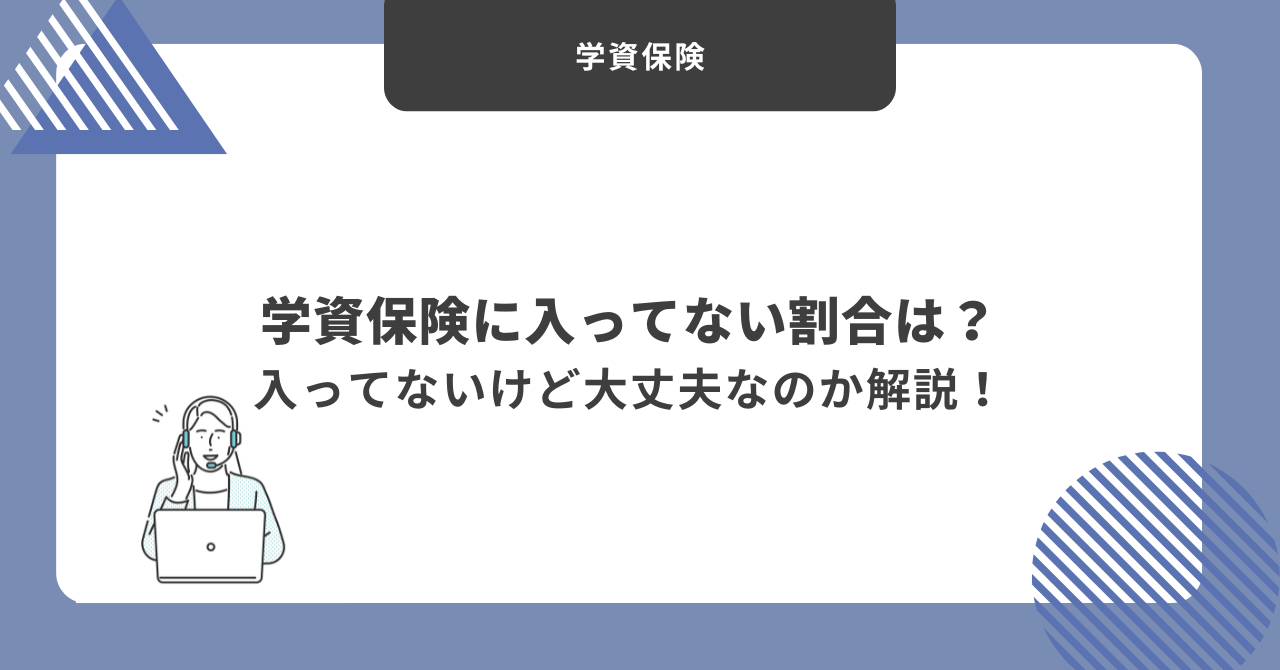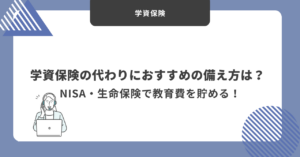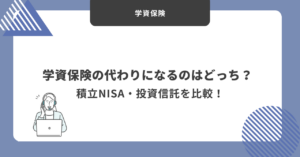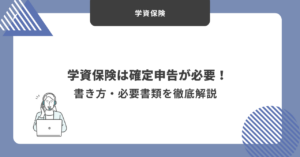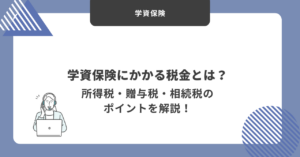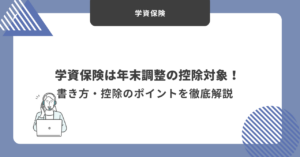学資保険に入っていないけど、大丈夫かな?
学資保険に入ってない人がどれぐらいいるのか割合を知りたい。
子どもの教育資金の準備として学資保険に加入する方は少なくないでしょう。
しかし、全家庭が学資保険に入っているわけではありません。
今回は、学資保険に入っていない割合や、入っていなくても大丈夫であるのかについて分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険に加入する必要があるのかが理解できるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの将来の教育資金を準備するための貯蓄型保険です。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払い、子どもが小学校・中学校・高校・大学に進学するタイミングで保険金を受け取る仕組みになっています。
死亡保障や医療保障がセットになっているプランもあり、教育資金の準備だけではなく「もしもの備え」としても利用されます。
子どもの将来の教育費に備えて加入する親や祖父母が多い保険です。
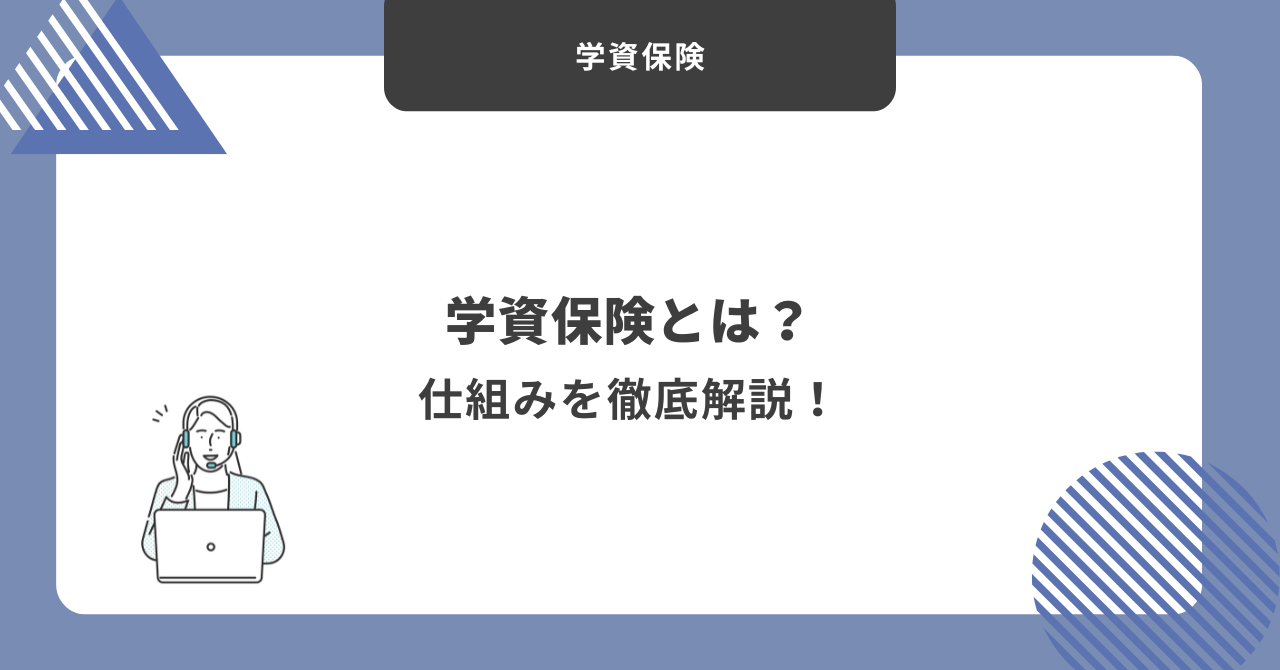
学資保険の必要性
子どもが幼稚園から大学まで進学するには、予想以上に多くの教育費が必要になります。
幼稚園から大学までに必要な教育資金は1,000万円~2,000万円以上かかるため、計画的に教育資金を準備しないといけません。
子どもを育てるためには、計画的な貯金が必要なことや、親に万が一のことがあった場合でも我が子の教育を支援できる保障が必要となります。
学資保険は子どもを育てるために必要であるといえるでしょう。
学資保険のメリット・デメリット
学資保険のメリットとデメリットは下記の通りです。
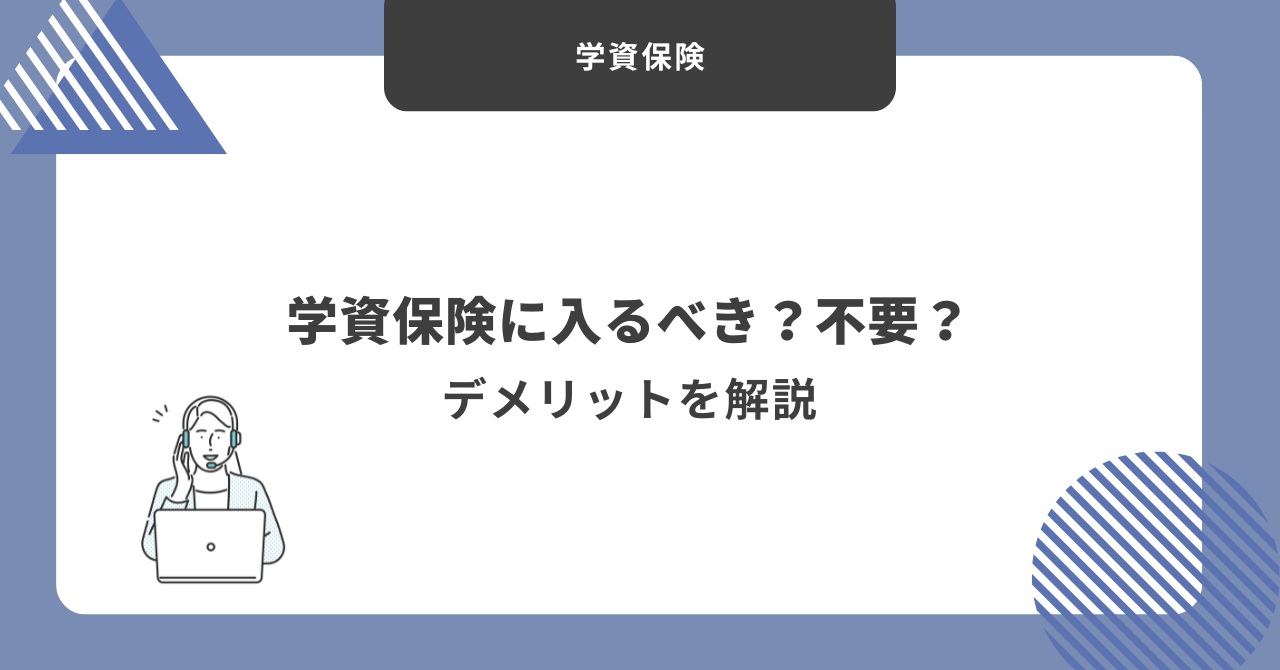
学資保険に入ってない割合は?
実際にどのくらいの家庭が学資保険に加入しているのか紹介します。
学資保険の加入割合
2025年のソニー生命の「子どもの教育資金に関する調査」1では、子どもを大学等へ進学させるための教育資金を準備している方法として、38.4%が学資保険を利用していると回答しました。
学資保険に加入していない理由としては、下記のような声が多く見られます。
・経済的な余裕がない
・学資保険や子どもの進学費用の積立に関する情報・知識が足りない
・投資など別の方法で準備している
1番多い教育資金の準備方法は銀行預金(54.3%)で、続いて学資保険、3番目に投資信託や積立NISA等の資産運用(24.1%)でした。
世帯年収別で見ると、資産運用で教育資金を準備しているのは世帯年収800万円以上がほとんどです。
2024年からの児童手当の拡充や、資産運用をする人が増えてきたことから、学資保険に加入している割合は4割程度となっています。
シングルマザーは学資保険に入ってない?
ひとり親世帯の中でも特にシングルマザーは家計のやりくりが大変なことが多く、学資保険の加入状況にも差が出る傾向があります。
シングルマザーの学資保険加入率
2019年版の全労済協会の「共済・保険に関する意識調査結果報告書」2では、ひとり親世帯の学資保険の加入率は21.2%でした。
ひとり親世帯が学資保険に加入している割合は2割程度と低くなっています。
シングルマザーが学資保険に加入するメリット
シングルマザーが学資保険に加入している割合はとても低いですが、ひとり親世帯だからこそ学資保険に加入するメリットもあります。
契約者である母親に万が一のことがあった場合でも、以後の保険料が免除され満期時には給付金が支払われます。
ひとり親世帯だからこそ、親に何かあった時に子どもの教育費にダイレクトに打撃を与える可能性が高いですが、学資保険で備えることによって子どもの教育資金を確保できます。
また、学資保険は強制的な積立という側面があるため、使い込みを防ぎながら教育資金を着実に準備できます。
医療特約などをつけることで、教育資金だけでなく病気やけがへの備えにもなる保険があることも魅力です。
学資保険に入ってない!すぐに入るべき人
学資保険はすべての人にとって必要とは限りません。
しかし、状況によっては、早めに加入することが将来の安心につながります。
・確実に教育資金を貯めたい人
・自分で貯金ができない人
確実に教育資金を貯めたい人
教育資金の準備にはお金がかかると分かっていても、日々の生活の中でお金をコツコツ貯めるのは意外と難しいものです。
そんな方にとって、学資保険は「自動的に貯まる仕組み」として活用できます。
強制的に保険料が引き落とされることで確実な貯蓄が可能で、満期でまとまった金額を受け取れます。
教育資金の見通しが立てやすいため、確実に教育資金を貯めたい方で学資保険に入っていない方は、すぐに加入することをおすすめします。
自分で貯金ができない人
「つい使ってしまって貯金ができない」「目先の出費を優先してしまう」というタイプの人には、強制力のある積立制度として学資保険がおすすめです。
契約者に万が一のことがあった場合でも、その後の保険料が免除され予定通りの給付金が支払われる仕組みがあるため、リスク対策としても優れています。
学資保険に入ってない!入る必要がない人

一方で、すべての人が学資保険に加入する必要があるわけではありません。
状況や資産形成の手段によっては、他の方法の方が良い場合もあります。
・十分な資産がある人
・コツコツ貯金ができる人
・保険料を支払うことが難しい人
十分な資産がある人
すでに教育資金を現金や他の金融資産で確保できている場合、学資保険に改めて加入する必要はありません。
流動性や柔軟性を重視した資産管理の方が学資保険よりも優れている場合があるでしょう。
コツコツ貯金ができる人
自分で毎月きちんと貯金ができ、計画的にお金を運用できる人であれば、学資保険に頼る必要がないでしょう。
積立NISAや投資信託を活用した運用を行っている場合は、学資保険よりもより高い利回りも期待できるため、学資保険を選択する必要はありません。
保険料を支払うことが難しい人
家計に余裕がない場合、無理に学資保険に加入してしまうと、途中で解約し元本割れするリスクがあります。
途中解約をすることで、加入していた期間に支払った保険料も無駄になり損をすることになります。
保険料を支払うことが難しい家庭は、まずは現金貯蓄を優先し家計が安定してから学資保険への加入を検討しましょう。
3歳で学資保険に入ってない場合!まだ遅くない?
「学資保険に加入するか迷っていたら、気づけば子どもがもう3歳」という方も少なくないでしょう。
3歳からの加入は、まだ間に合うのかについて解説します。
人気の学資保険は加入年齢が0~3歳までの場合がある
多くの学資保険は、加入年齢を0歳〜3歳までに設定しており、それを過ぎると申込できない場合があります。
特に返戻率が高い人気の保険商品ほど制限があることが多いため、3歳はラストチャンスとも言えるタイミングです。
加入しようか迷っている学資保険がある場合は、加入年齢などの条件を把握しておきましょう。
早く加入する方が保険料が安い
学資保険の保険料は、契約時の年齢が若いほど安くなるのが一般的です。
0歳で加入した場合と3歳で加入した場合とでは、同じ満期金額でも月々の保険料に数千円の差が出ることもあります。
また、万が一の保障があるため、加入する気がある方は早く契約した方が良いでしょう。
返戻率が下がる
加入年齢が上がると保険料の払込期間が短くなるため、返戻率が低くなる傾向にあります。
返戻率は、学資保険を選ぶ際の大きなポイントです。
少しでも返戻率が高い方がお得になるため、3歳よりも0歳で加入することをおすすめします。
小学生になる6歳で学資保険に入ってない場合!注意点は?
お子さんが6歳(小学校入学)となると、学資保険加入にはいくつか注意すべきポイントがあります。
親の年齢が上がると保険料が高くなる
保険は、被保険者(子ども)だけではなく、契約者(通常は親)の年齢によっても保険料が変わります。
親の年齢が上がるとリスクも増し、保険料が高くなるため注意が必要です。
また、親の健康状態によっては加入できないこともあります。
年齢が若く、健康状態に問題がない間に加入しましょう。
払込期間を短くすることで返戻率を上げる
6歳で学資保険に加入する場合、「10年払込」「12歳まで払込」など、払込期間を短く設定することで返戻率を高めることが可能です。
しかし、月々の保険料の負担は大きくなるため、家計とのバランスを見て判断する必要があります。
加入年齢が6歳までと制限される場合がある
学資保険は「子どもの年齢が6歳まで」という加入条件を設けている場合が多いです。
7歳になると申込自体ができなくなる商品もあるため、「入るなら6歳の今が最後のタイミング」という場合もあります。
気になっている学資保険がある場合は、必ず加入年齢を確認して早めに契約することをおすすめします。
小学生(6歳)で学資保険に入ってない場合!どうしよう?
ここまでの情報から分かる通り、6歳は学資保険加入のギリギリラインです。
ただし、無理に学資保険に加入する必要はありません。
小学生から学資保険に入るのはおすすめできない
学資保険は長期でゆっくり積み立てる保険のため、加入時期が遅くなると下記のようなデメリットがあります。
そのため、6歳以降の加入はあまりおすすめできません。
教育資金を貯める他の方法
6歳で学資保険に加入することはおすすめできませんが、他の教育資金を貯める方法はまだあります。
これらの方法を活用すれば、学資保険に頼らず教育資金の準備は十分可能です。
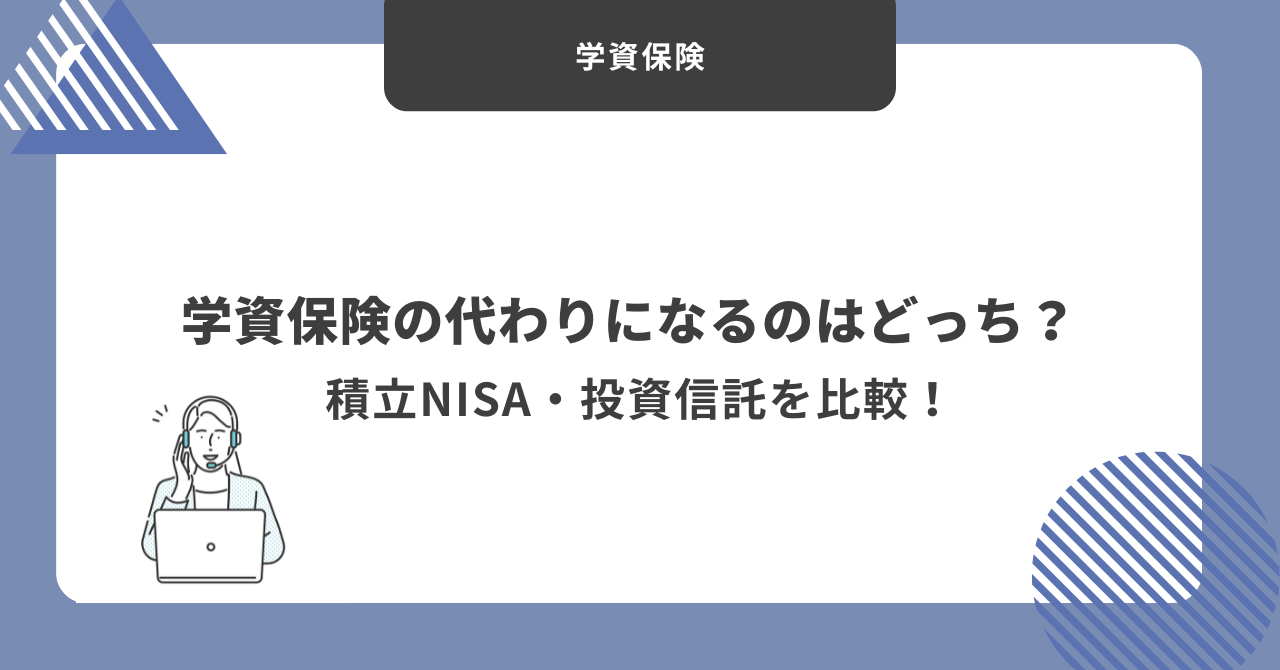
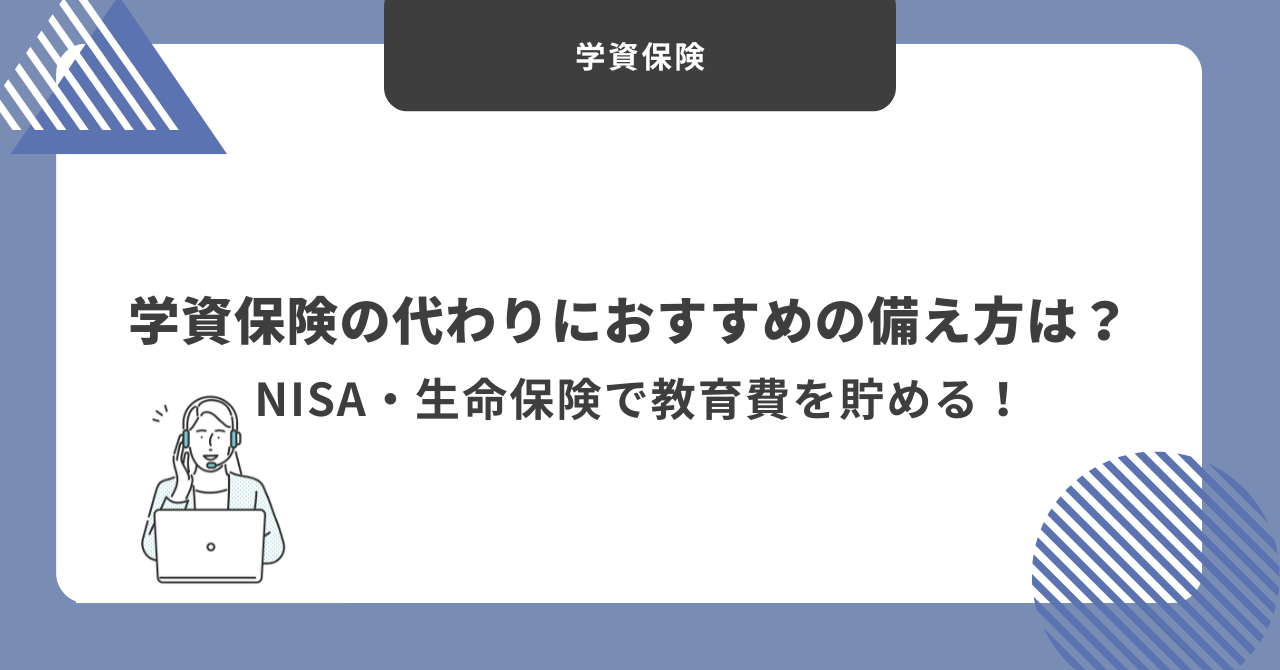
まとめ
学資保険は加入が義務付けられている訳ではありませんが、子どもがいる家庭は4割が加入している保険です。
加入できる年齢など条件があるため、検討中の方は早めに契約することをおすすめします。
学資保険に入らなくてもしっかりと他の方法で教育資金を準備できる方にとっては必要はありませんが、確実に教育資金を貯めたい方には向いているでしょう。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。