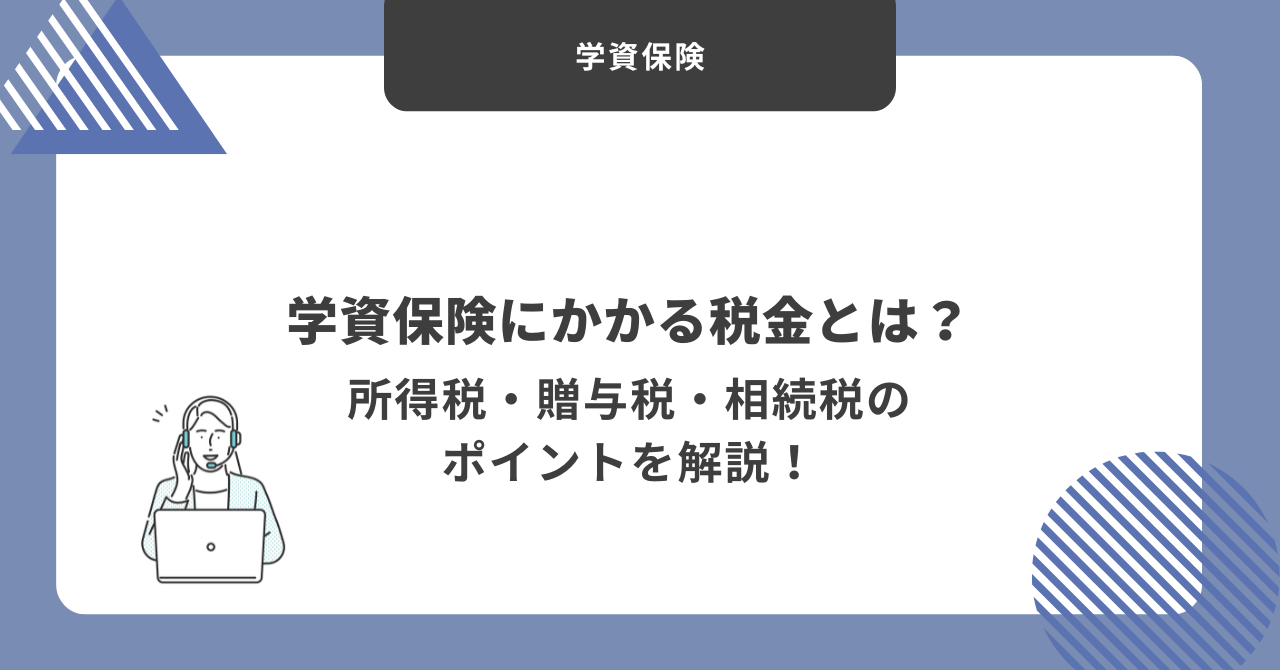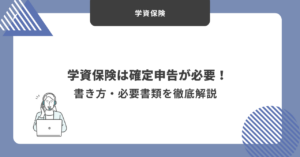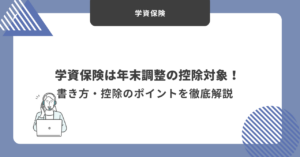学資保険で保険金を受け取る時、税金ってかかるのかな?
税金が一番かからない方法で学資保険に加入するにはどうしたら良いのだろう?
お子様の教育資金を準備するために学資保険に加入する方も多いでしょう。
今回は、学資保険のお祝い金や保険金にどのような税金がかかるかを分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険にかかる所得税・贈与税・相続税のポイントを理解することができるでしょう。
学資保険にかかる税金とは?
学資保険の受け取りに際しては、所得税・贈与税・相続税のいずれかが課税される可能性があります。
課税の種類は、保険料を支払った契約者と保険金を受け取る人である受取人の関係によって異なります。
所得税
契約者と受取人が同一人物である場合、保険金は所得とみなされ一時所得や雑所得として課税される可能性があります。
保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」となり、最高50万円の特別控除が適用されます。
保険金を年金として受け取る場合は「雑所得」となり、金額が20万円以下の場合は所得税はかかりません。
贈与税
契約者と受取人が異なる人物の場合、保険金の贈与と見なされた場合に適用されます。
しかし、学資保険では契約者と受取人が同一の場合が多いため、贈与税の対象になることは少ないでしょう。
相続税
契約者が死亡し、保険金が死亡保険金として支払われた場合に適用されます。
一覧表
| 契約者と受取人 | 受け取り方 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 契約者と受取人が同じ | 一括 | 所得税(一時所得) |
| 年金 | 所得税(雑所得) | |
| 契約者と受取人が異なる | 一括・年金 | 贈与税 |
| 契約者が死亡 | – | 相続税 |
契約者と受取人が同じ:一括受け取りのケース
契約者が保険料を払い、保険金も一括で受け取った場合、保険金は「一時所得」として課税対象になります。
一時所得の計算
一時所得の計算方法は下記の通りです。
一時所得 = 保険金 − 支払保険料総額 − 特別控除(最高50万円)
課税対象 = 一時所得 × ½
支払保険料総額:270万円
保険金:300万円
一時所得:300万円-270万円-50万円=-20万円
課税対象となる一時所得は0円のため、税金はかかりません。
契約者と受取人が同じ:年金受け取りのケース
年金形式で受け取る場合、「雑所得」として扱われます。
雑所得の計算
年金形式での計算方法は下記の通りです。
雑所得 = その年に受け取った祝金-その年に受け取った祝金×(支払保険料総額÷祝金総額)
支払保険料総額:270万円
祝金:300万円
その年に受け取った祝金:75万円
雑所得:75万円-75万円×(270万円÷300万円)=7万5千円
雑所得は、特別控除はなく、他の所得と合算して½にする仕組みはありません。
また、一定の要件を満たす給与所得者は雑所得の金額が20万円以下の場合、申告が不要です。
自営業者は雑所得の金額をそのまま申告する必要があるため、注意しましょう。
契約者と受取人が違うケース
契約者が保険料を支払い、受取人が別の人の場合には「贈与税」または「相続税」の課税対象となります。
贈与税の計算
契約者が親で、受取人が子どもとなる場合、贈与を受けたとみなされるでしょう。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える贈与に課税されます。
贈与税=(保険金−基礎控除110万円)×税率-控除額
税率は受取額に応じて10%〜55%まで累進課税されます。
満期保険金が200万円の場合の税金は?
満期保険金が200万円の場合の、税金の例を紹介します。
一番多いケースである、契約者と受取人が父親と仮定します。
支払保険料総額:150万円
満期保険金:200万円
200万円-150万円-50万円(特別控除)=0円
課税なし
支払保険料総額:120万円
満期保険金:200万円
200万円-120万円-50万円(特別控除)=30万円
30万円×1/2=15万円
15万円が所得税・住民税の課税対象額になる
学資保険を解約した場合!税金はかからない?

学資保険を途中で解約して解約返戻金を受け取った場合も、所得税や贈与税の課税対象になる可能性があります。
ただし、下記の場合は非課税です。
・解約返戻金が支払った保険料総額以下である
・一時所得の計算後、課税対象額が0円になる場合
解約返戻金が所得税として課税対象となる場合(契約者・受取人が同一)は、税金がかかるケースはあまりありません。
解約返戻金-払込保険料-50万円×1/2
しかし、贈与税として課税対象となる場合(契約者・受取人が違う)は、税金がかかり損をする可能性が高いでしょう。
解約返戻金-110万円×税率-控除額
また、学資保険は早期に解約すると元本割れしやすく、税金の心配は少ないですが損失リスクが高いため注意が必要です。
孫のために祖父母が学資保険に加入できる?
祖父母が孫の教育資金を準備するために学資保険に加入することは可能です。
しかし、税務上の取り扱いには注意が必要です。
祖父母が契約した学資保険にかかる税金
契約者:祖父母
被保険者:孫
受取人:親か孫
上記のような場合、保険金の受取時に贈与税が課される可能性があります。
祖父母が保険料を払い、孫やその親が保険金を受け取ると「贈与」とみなされます。
年間に贈与される総額が110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 契約者・受取人が同一 | 祖父 | 孫 | 祖父 | 所得税 |
| 契約者・受取人が異なる | 祖父 | 孫 | 孫 | 贈与税 |
| 契約者・被保険者・受取人が異なる | 祖父 | 孫 | 孫の父 | 贈与税 |
祖父母が孫のために学資保険に加入する場合の注意点
・加入できる年齢に上限がある
・健康状態の告知がある
・親の同意が必要
多くの学資保険では、契約者の年齢上限が60~75歳程度に設定されています。
保険に加入する際には健康状態の告知が求められ、持病や既往歴によっては加入が制限されることもあります。
また、被保険者が未成年(孫)であるため、加入には親権者(親)の同意が必要です。
保険会社によっては「祖父母と孫が同居していること」や「生活を共にしていること」の証明書類の提出を求められることもあるため、注意が必要です。
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象
学資保険は、「一般生命保険料控除」の対象となるため、年末調整や確定申告で申告をすれば所得税・住民税の軽減が可能です。
学資保険の生命保険料控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された学資保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払額の全額 |
| 25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払額の全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された学資保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払額の全額 |
| 20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払額の全額 |
| 12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
年末調整と確定申告で申告しなければ控除されないため、必ず忘れずに申告しましょう。
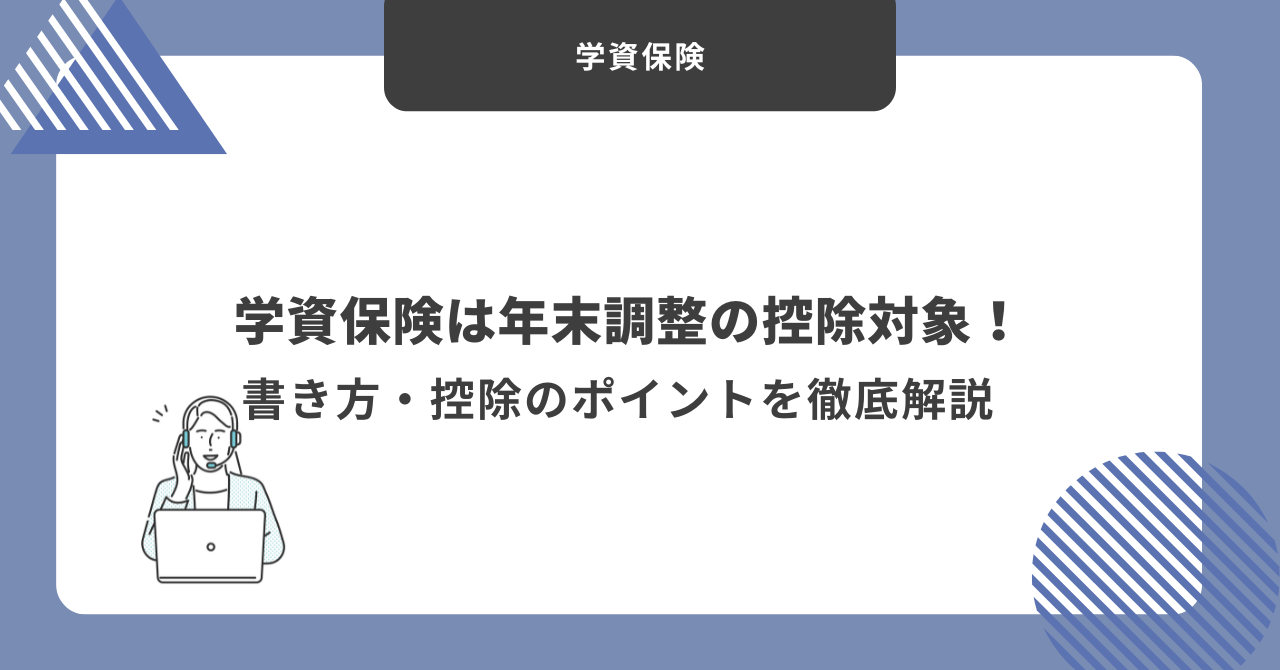
学資保険の税金が気になる場合のポイント
学資保険は、契約形態や受け取り方法によって税金の種類や課税額が大きく変わります。
下記のポイントを押さえて、税負担を最小限に抑えましょう。
・契約者と受取人を同じにする
・年金受け取りを避けた方が良い場合もある
契約者と受取人を同じにする
税金対策として最も重要なのが、「契約者」と「受取人」を同一人物に設定することです。
契約者と受取人が同じである場合は、所得税の対象となります。
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税や相続税の対象になる可能性があります。
一時所得には50万円の特別控除や課税額1/2ルールがあるため、比較的負担が軽く済みます。
そのため、契約者と受取人を同一で契約することがおすすめです。
年金受け取りを避けた方が良い場合もある
学資保険によっては、「年金形式」で保険金を受け取れるタイプもありますが、税金面では注意が必要です。
年金受け取りは、雑所得として課税されるため毎年の所得に加算されます。
所得が高い方の場合、所得税・住民税の税率が上がるのでトータルの課税額が増える可能性が考えられるでしょう。
そのため、特に所得が高い方や学資保険以外で雑所得が多い方は、年金受け取りよりも一括受け取りの方がおすすめです。
まとめ
学資保険を保険金を受け取る場合、受け取り方によって所得税・贈与税・相続税などの税金がかかります。
契約者と受取人を同じに設定するケースが一番税金がかからない可能性が高いため、おすすめです。
税金の計算については専門知識が必要になるため、保険会社や税理士に相談しましょう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。