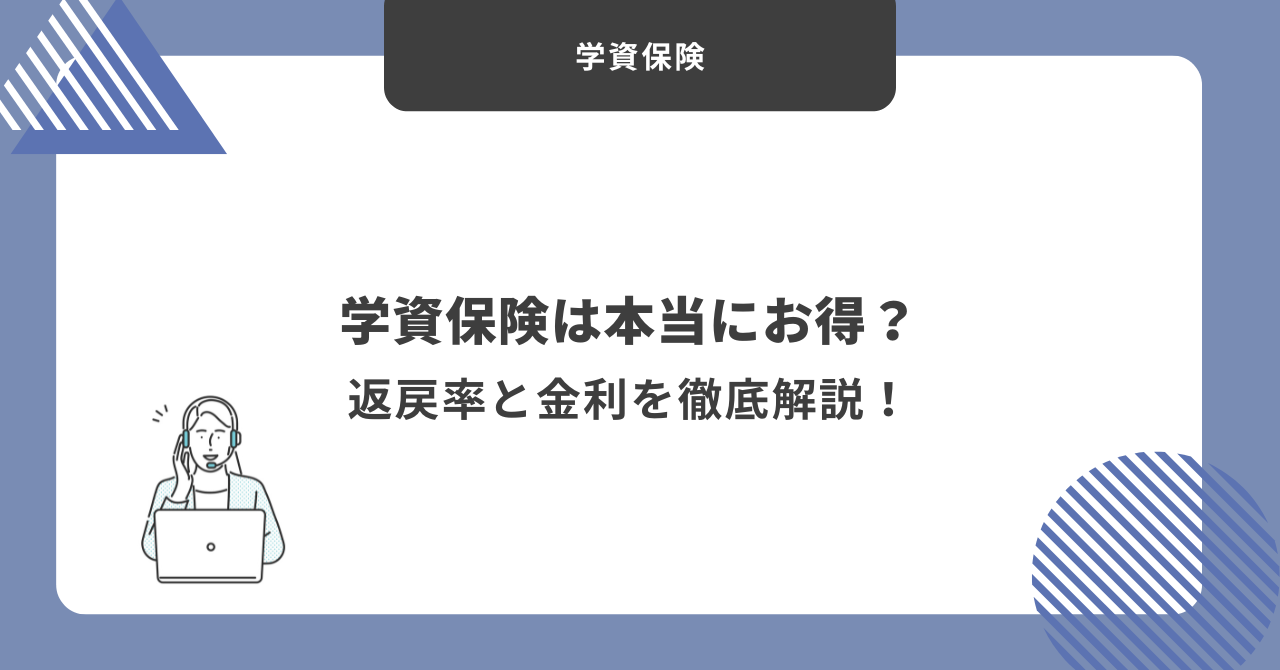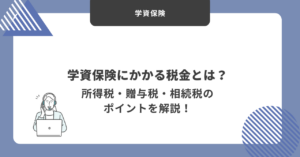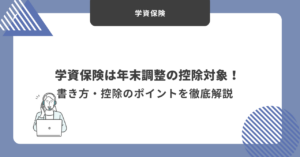学資保険でよく聞く「返戻率」って何のこと?
学資保険の返戻率を少しでも高くするためにできることはあるのかな?
学資保険を検討している親にとって、返戻率は一番気になるポイントでしょう。
少しでも返戻率の高い学資保険に加入して、お子さんの教育資金を貯めたいと考える親は多いと思います。
今回は、学資保険の返戻率について分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の返戻率を高くする方法や注意点を理解することができるでしょう。
学資保険は本当に必要?
まずは学資保険が本当に必要であるかについて、学資保険の基礎知識と必要性について解説します。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの将来の教育資金を準備するための貯蓄型保険です。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払い、子どもが小学校・中学校・高校・大学に進学するタイミングで保険金を受け取る仕組みになっています。
死亡保障や医療保障がセットになっているプランもあり、教育資金の準備だけではなく「もしもの備え」としても利用されます。
子どもの将来の教育費に備えて加入する親や祖父母が多い保険です。
学資保険の必要性
教育費は年々上昇しており、大学進学時には数百万円の費用が必要となる可能性が高いです。
こうした出費に備えるには、計画的な貯蓄が不可欠と言えるでしょう。
学資保険は、強制的に貯蓄ができるため、コツコツと自分で貯めることができない方にとっては必要不可欠な保険です。
しかし、低金利時代の現在では、返戻率や流動性も考慮して他の教育資金を準備する選択肢と比較することが重要となってきます。
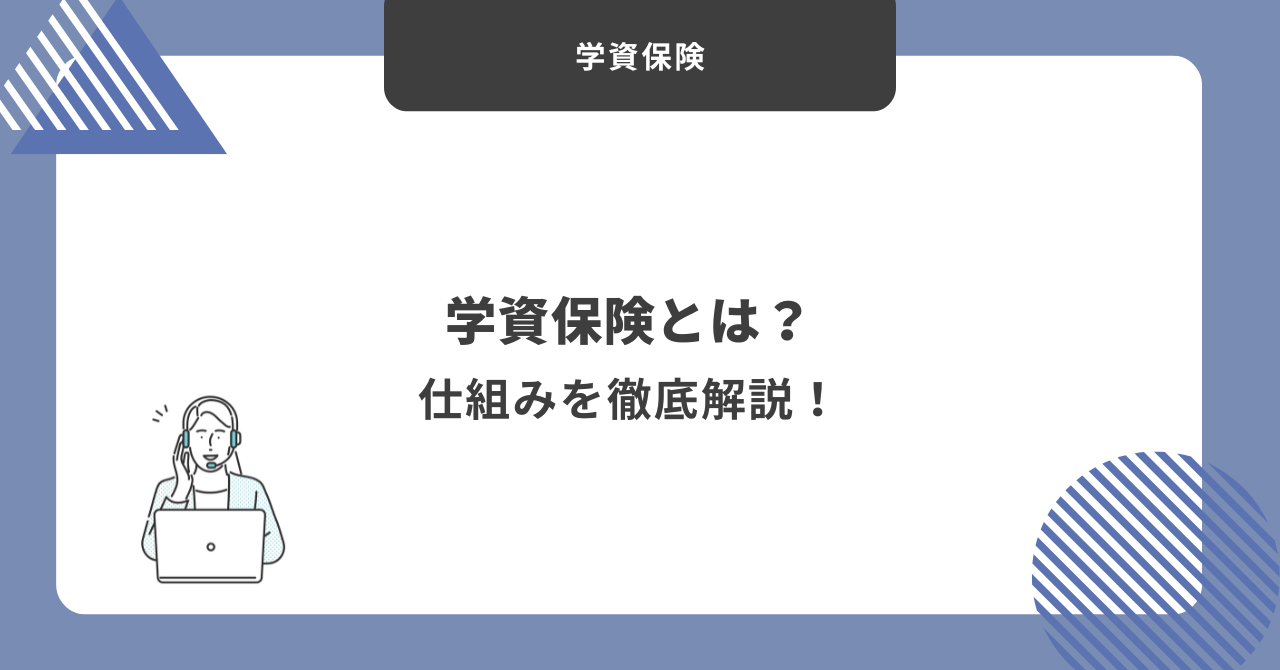
学資保険の返戻率
学資保険の返戻率について、解説します。
学資保険の返戻率とは?
返戻率とは、支払った保険料総額に対して、将来受け取れる保険金の割合を示した数値です。
保険料の総支払額:100万円
将来受け取れる保険金:105万円
返戻率:105%
返戻率が100%を超えている場合は、支払った保険料よりも受け取れる保険金額の方が高くなるため、お得と言えます。
逆に返戻率が100%を下回る場合は、支払った保険料よりも受け取れる保険金額の方が少なくなり、「元本割れ」になります。
そのため、返戻率が高いほど「お得」と思う方も多いでしょう。
しかし、返戻率だけで学資保険を選択することはおすすめできません。
返戻率に加えて、保障内容もしっかりと把握した上で、ご家庭に合ったプランを選ぶことが大切です。
学資保険の返戻率の計算は?
返戻率の計算方法は、下記の通りです。
返戻率=受取総額÷支払総額×100
保険料支払総額:200万円
受取総額:210万円
計算方法:210万円÷200万円×100=105%
返戻率:105%
しかし、保険金を受け取る時期や、加入する時期、支払方法(年払いなど)によって、多少ですが保険料の総額が異なるため返戻率は変動します。
加入する時に保険会社に、払込む保険料と期間、将来受け取る保険金の時期と総額を確認することが重要です。
金利の仕組みが学資保険へ与える影響は?
金利の種類
学資保険に関係する金利は主に以下の通りです。
| 予定利率 | 保険会社が契約者に「このくらいの利率で資産を運用しますよ」とあらかじめ定める金利のこと。 保険会社が契約時に設定する、保険料の運用利率。 高ければ返戻率も高くなりやすい。 |
| 実質利回り | 実際に受け取る金額と支払った保険料を元に計算される「実質的な運用成果」のこと。 例えば、10年間で100万円払って、110万円戻ってきた場合の利回りは 年平均約1%程度。 |
金利で返戻率はどう変わる?
高金利時代(1990年代)では予定利率が3%〜5%と高く、返戻率も120%を超える学資保険のプランは珍しくありませんでした。
しかし、現在のような超低金利時代では、予定利率が1%を下回ることもあり、返戻率も100%前後に落ち着いています。
金利の変化は学資保険の返戻率に直接関係しています。
そのため、現在では学資保険に加入する目的は「増やす」より「備える」ことを目的で加入することが主流になっています。
| 金利が高い昔 | ・予定利率が高く設定されていた(例:3%〜5%) ・学資保険の返戻率では120%超のプランも存在 ・「預けるだけで増える」時代だった |
| 金利が低い現在 | ・予定利率は1%を下回ることもある ・返戻率は100%前後、または100%未満の元本割れするプランもある ・「保障付き貯蓄」としての意味が強まっている |
現在の学資保険の考え方
現在の学資保険は、貯蓄を大きく増やすことは期待できないが、計画的な積立+万が一の備えになるという考え方で加入する方が多いです。
そうは言っても返戻率を重視したい場合は、短期払いや一括払いで保険料を短い期間で支払終えるプランで加入することを検討するのが良いでしょう。
また、貯蓄重視で増やすことを目的とする場合は、「積立NISA」や「投資信託」と比較して検討することをおすすめします。
親に万が一のことがあった場合の保障や支払い免除を重視する場合は、学資保険が向いています。
学資保険に加入する目的をしっかりと考えた上で、どのような方法で教育資金を貯めるかを考えることが重要です。
学資保険の返戻率を高くするには?

学資保険の返戻率を少しでも高くするためには、いくつかのポイントがあります。
・保険料をまとめて支払う
・保険料の払込期間を短くする
・保険金を受け取るまでの期間を長く設定する
・祝金を受け取らないプランを選択する
保険料をまとめて支払う
学資保険の保険料の支払い方法は、下記の通りさまざまです。
・一時払い
・年払い
・半年払い
・月払い
保険料を契約時に一括で支払う「一時払い」の方法が、一番返戻率が高くなります。
保険会社が資金を早く受け取れるため、予定利率が有利に反映され返戻率が上がるからです。
しかし、一時払いはまとまった資金が必要となるため、無理のない資金計画が重要になります。
家計の負担にならないように支払い方法を選択しましょう。
保険料の払込期間を短くする
保険料の払込期間を10年など短く設定すると、返戻率が上がります。
保険会社が資金を運用できる金額が大きくなることや、運用期間が長くなるからです。
同じ保障内容でも、20年払いより10年払いの方が「運用効率が良い」とされます。
しかし、月々の保険料は高くなるので負担は増えるため、家計に余裕がある場合におすすめの方法です。
保険金を受け取るまでの期間を長く設定する
保険金の受取時期が遅いほど、返戻率が高くなります。
保険会社は、保険料の一部を運用しているため、資金を長く運用できるからです。
例えば、高校入学時ではなく、大学進学時を受取時期に設定することで返戻率が高くなるため、保険金の受取時期をよく考えて加入しましょう。
祝金を受け取らないプランを選択する
学資保険には、小学校・中学校・高校・大学へ入学する節目のタイミングで祝い金を受け取れるプランがあります。
節目でお祝い金を受け取れるプランは魅力的に見えますが、その分保険会社の運用期間が短くなるため、返戻率が下がる傾向にあります。
満期まで受け取らずに運用を続けるプランの方が返戻率が良いため、受け取りのタイミングも重要です。
教育費に困らない場合は、祝い金を受け取らないプランがおすすめです。
返戻率の注意点
返戻率について解説し、「返戻率が高い方が良い」と思う方も少なくないでしょう。
しかし、必ずしも返戻率が高い学資保険が良いとは限りません。
返戻率の注意点を2点、紹介します。
・返戻率だけで判断するとリスクを見落とす
・インフレには対応していない
返戻率だけで判断するとリスクを見落とす
返戻率の高いプランは、途中解約時に大きく元本割れするリスクが考えられます。
また、「保障がほとんどついていない貯蓄型」など、万一に備える機能が弱い可能性も高いです。
高い返戻率にするために「大切な保障」を削ったり、「契約の自由度」を下げている場合もあります。
返戻率だけを基準にせず、保障内容や契約条件も総合的に確認しましょう。
インフレには対応していない
返戻率が高い学資保険に加入して、将来受け取れるお金が増えていても、そのときの物価が上がっていたら価値は下がります。
返戻率が105%だったとしても、将来の物価が10%上がっていたら実質的な価値は減ることになるでしょう。
学資保険は額面が保証されますが、「物価変動には対応していない」という特徴があります。
そのため、インフレリスクを考慮した資産運用と併用するのがおすすめです。
まとめ
学資保険の返戻率とは、払い込んだ保険料に対して受け取れる金額の割合を示した数字です。
返戻率が高い方がお得ではあるが、返戻率だけで保険プランを決めるとリスクもあります。
家計の状況や保障内容をしっかりと見極めてライフプランに合った学資保険に加入することをおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。